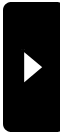2015年01月06日
匠が物申す第30弾・「風水のお話し」
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
匠が物申すも30話になり、
ここで、しばらくお休みをさせて頂きたいと思っている棟梁です。
次回機会があれば、また再開したいと思っていますので、
しばらくお時間を頂きたく宜しくお願いします。
「大工が教える風水のお話」

大工や設計士も、風水については
それなりに知識を持っています。
そして、表鬼門(北東)、裏鬼門(南西)、荒神様など
方角を配慮して設計しているんですよ。
でも、風水も、諸説ありますので、
100%良い家を建てようとはしません。
例えば、土地が300坪あって、
そこに100坪の家を建てられるのなら
完全に吉相の家を設計することができるかもしれません。
でも、50坪の土地に30坪の家を建てるなら
絶対に、何らかの「凶」が入ってしまうものなんです。
一つひとつにこだわり過ぎるより、
住まう人が、その後、家を綺麗にしてもらうこと
土地の神様がいる土地の角は、
きれいに保ち、踏まないことをお勧めします。
土地の三つ角(家のなかではなく)は、すべて
極力、踏まないようにしたほうがいいとされています。
特に、北西、北東、南西の角には、神様がいると言われています。
南西の角には、柊を植えると良いなどと言われますよね。
もしも、すでに駐車場などになっているなら、
四つ角に、お花などを置いてあげるといいでしょう。
プランターを置いて
そのうえを歩いて踏まないようにしておけばいいのです。
踏まないこと。
そして、清潔にしておくこと。
それだけでも、運気を上げることができるようです。
もしも、北東に水回りがあるのなら
・風通しをよくしておくこと
・清潔にすることと
・刃物(顔そり)を置きっぱなしにしておかないこと
・白いものを置いて明るくすること
などで、運気を上げることができるそうです。
結局は、自分が住んでいる家を、長持ちさせようと
きれいにしたり、手入れをしたり、
住んでいる家族みんなが
どれだけ家を大切にできるかということかもしれませんね。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
匠が物申すも30話になり、
ここで、しばらくお休みをさせて頂きたいと思っている棟梁です。
次回機会があれば、また再開したいと思っていますので、
しばらくお時間を頂きたく宜しくお願いします。
「大工が教える風水のお話」

大工や設計士も、風水については
それなりに知識を持っています。
そして、表鬼門(北東)、裏鬼門(南西)、荒神様など
方角を配慮して設計しているんですよ。
でも、風水も、諸説ありますので、
100%良い家を建てようとはしません。
例えば、土地が300坪あって、
そこに100坪の家を建てられるのなら
完全に吉相の家を設計することができるかもしれません。
でも、50坪の土地に30坪の家を建てるなら
絶対に、何らかの「凶」が入ってしまうものなんです。
一つひとつにこだわり過ぎるより、
住まう人が、その後、家を綺麗にしてもらうこと
土地の神様がいる土地の角は、
きれいに保ち、踏まないことをお勧めします。
土地の三つ角(家のなかではなく)は、すべて
極力、踏まないようにしたほうがいいとされています。
特に、北西、北東、南西の角には、神様がいると言われています。
南西の角には、柊を植えると良いなどと言われますよね。
もしも、すでに駐車場などになっているなら、
四つ角に、お花などを置いてあげるといいでしょう。
プランターを置いて
そのうえを歩いて踏まないようにしておけばいいのです。
踏まないこと。
そして、清潔にしておくこと。
それだけでも、運気を上げることができるようです。
もしも、北東に水回りがあるのなら
・風通しをよくしておくこと
・清潔にすることと
・刃物(顔そり)を置きっぱなしにしておかないこと
・白いものを置いて明るくすること
などで、運気を上げることができるそうです。
結局は、自分が住んでいる家を、長持ちさせようと
きれいにしたり、手入れをしたり、
住んでいる家族みんなが
どれだけ家を大切にできるかということかもしれませんね。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2014年12月04日
匠が物申す第29弾
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
突然の寒さに治りかけの風邪もぶり返し、
喉のイガイガが治おらず、困っている棟梁です。
さて、匠が物もうすも29回目を迎える事になり、
皆さんから、もっと家に関する事教えてくださいと、
言われるようになり少しでもお役に立てていれる事が、
最近の励みなっています。
今日は、名古屋で毎年恒例の会議です。
いつもと違うこんな格好で電車に乗って行きます。

棟梁の思いから、このような事を書いてあります。
様々なご意見があると思いますが、ご理解して下さい。
究極のエコ住宅「古民家」は手入れが必要
人気のある「古民家」ですが、
僕らが建てているのと同じ「日本家屋」です。
行かれたことのある方は、ご存じだと思いますが
天井が高いということは、冬は、ど寒いんです(笑)。
だからこそ、暖炉や囲炉裏が必要だったんですね。
家のなかで火を焚くので、温かい空気が回り暖を取れる。
そして、そこに家族が集まるわけです。
今は、囲炉裏よりも、薪ストーブが
おしゃれで人気のようです。
確かに素敵ですが、薪を用意するのが結構難しいんです。
簡単には入手しにくいし、
できあがった薪を買う場合、ランニングコストが意外に高くつきます。
そのため、自分で薪を割って用意するとなると
冬が来る前に、薪の準備に何日もかけることになります。
それを承知のうえで、薪割りを楽しめる人なら
薪ストーブもいいのではないでしょうか。
薪は「広葉樹」を使ったほうがいいと言われています。
広葉樹のほうが針葉樹よりも火持ちがいいからですが、
針葉樹が薪に使えないわけではありません。
もちろん、天井さえちゃんと張れば
古民家でも、暖を取ることはできます。
昔は、やはり、すきま風が多かったので
家全体が寒かったんですね。
となると、囲炉裏が必要になってくる。
とはいえ、囲炉裏を使う場合、
天井が低いと煙がちゃんと抜けてくれない。
だからこそ、天井が高くないといけないし
「茅葺き屋根」だったんですね。
ちゃんと、理にかなっているんです。
そして、この囲炉裏の煙も役に立ちます。
茅葺き屋根の骨組みは、竹なんですが、
囲炉裏の煙に長年いぶされてきたスス竹は
「虫除け効果」があるんです。
すべてが、うまく理にかなっているわけです。
よくできていますよね。
スス竹は、現在では、希少価値があるんだそうですよ。
古民家の外壁には、よくコールタールを塗られていました。
これも、やはり塗り直しが必要です。
みなさんが「黒くて太い梁」に魅せられていますが
あれは、50年間、米のとぎ汁や小糠を使って
柱を磨き続けてきたから、艶が出て黒いんです。
「手入れ」をし続けた結果の、味わいなんですね。
新築のころは、やはりナチュラルな明るい柱だったわけです。
古民家に暮すということは
自然の暑さ、寒さを受け入れるということ。
そして、家を大切に「手入れ」し続けることが好きじゃなきゃ
古民家で暮らすのは難しいかもしれません。
僕もぜひ、いつか、土間や囲炉裏のあるような
古民家風の家を造ってみたいと思っています。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
突然の寒さに治りかけの風邪もぶり返し、
喉のイガイガが治おらず、困っている棟梁です。
さて、匠が物もうすも29回目を迎える事になり、
皆さんから、もっと家に関する事教えてくださいと、
言われるようになり少しでもお役に立てていれる事が、
最近の励みなっています。
今日は、名古屋で毎年恒例の会議です。
いつもと違うこんな格好で電車に乗って行きます。

棟梁の思いから、このような事を書いてあります。
様々なご意見があると思いますが、ご理解して下さい。
究極のエコ住宅「古民家」は手入れが必要
人気のある「古民家」ですが、
僕らが建てているのと同じ「日本家屋」です。
行かれたことのある方は、ご存じだと思いますが
天井が高いということは、冬は、ど寒いんです(笑)。
だからこそ、暖炉や囲炉裏が必要だったんですね。
家のなかで火を焚くので、温かい空気が回り暖を取れる。
そして、そこに家族が集まるわけです。
今は、囲炉裏よりも、薪ストーブが
おしゃれで人気のようです。
確かに素敵ですが、薪を用意するのが結構難しいんです。
簡単には入手しにくいし、
できあがった薪を買う場合、ランニングコストが意外に高くつきます。
そのため、自分で薪を割って用意するとなると
冬が来る前に、薪の準備に何日もかけることになります。
それを承知のうえで、薪割りを楽しめる人なら
薪ストーブもいいのではないでしょうか。
薪は「広葉樹」を使ったほうがいいと言われています。
広葉樹のほうが針葉樹よりも火持ちがいいからですが、
針葉樹が薪に使えないわけではありません。
もちろん、天井さえちゃんと張れば
古民家でも、暖を取ることはできます。
昔は、やはり、すきま風が多かったので
家全体が寒かったんですね。
となると、囲炉裏が必要になってくる。
とはいえ、囲炉裏を使う場合、
天井が低いと煙がちゃんと抜けてくれない。
だからこそ、天井が高くないといけないし
「茅葺き屋根」だったんですね。
ちゃんと、理にかなっているんです。
そして、この囲炉裏の煙も役に立ちます。
茅葺き屋根の骨組みは、竹なんですが、
囲炉裏の煙に長年いぶされてきたスス竹は
「虫除け効果」があるんです。
すべてが、うまく理にかなっているわけです。
よくできていますよね。
スス竹は、現在では、希少価値があるんだそうですよ。
古民家の外壁には、よくコールタールを塗られていました。
これも、やはり塗り直しが必要です。
みなさんが「黒くて太い梁」に魅せられていますが
あれは、50年間、米のとぎ汁や小糠を使って
柱を磨き続けてきたから、艶が出て黒いんです。
「手入れ」をし続けた結果の、味わいなんですね。
新築のころは、やはりナチュラルな明るい柱だったわけです。
古民家に暮すということは
自然の暑さ、寒さを受け入れるということ。
そして、家を大切に「手入れ」し続けることが好きじゃなきゃ
古民家で暮らすのは難しいかもしれません。
僕もぜひ、いつか、土間や囲炉裏のあるような
古民家風の家を造ってみたいと思っています。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2014年11月17日
匠が物申す第28弾
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
昨日は、37.8度まで熱が出てしまい、
半日ダウン・・・
今日も、熱っぽかったんですが、しっかり仕事をした棟梁です。
さて、匠が物申すも今回で28回目になります。
いろんな方の考え方がありますが、
棟梁の思った事を綴っているので、ご理解して頂きたいと思っています。、
*大工に頼むと、工期が長い分だけ高いのでは?
アンケートに答えていただきまして
本当にありがとうございました。
おかげさまで、個人が収集するにしては
たくさんの回答が集まったようです。
そして、わかったのは、
やはり「日本家屋は高いのではないか?」
という印象をお持ちの方が多いことでした。
豊橋は、37万都市です。
僕は10,000分の1である37人のお客様がいらっしゃれば
生計が成り立つので、それで充分だと考えています。
欲張るつもりはありません。
とはいえ、まだ、37人には達していませんが。
残念ながら、昨今では、みなさんの感覚が、
「家を建てる」よりも「家を買う」になっています。
そして、不況の影響もあり、家を選ぶ基準として
「価格」を挙げる方も多いのが現実です。
確かに、価格は気になりますよね。
「工期が長い分、高くなるのではないか」
と言われることがありますが、それはありません。
例えば、3000万円で家を建てるとします。
ハウスメーカーで建てるなら、
確かに、工期3ヶ月でできるでしょう。
でも、本社利益、営業所経費、人件費、広告宣伝費、開発費等
などかかりますので
純粋に、現場で動く大工の人件費と、材料費だけに
支払われている金額ではないわけです。
大工が、3000万円いただいて建てるなら
確かに、工期は8ヶ月かかるかもしれませんが、
それは、それ相応の肯定を経ている理由があるだけです。
金額については、材料費と、人件費だけで
そのほとんどを占めていることになります。
その金額いっぱいの仕事をさせていただくことができるのです。
僕としては、それで充分です。
このカラクリに触れることは御法度だろうと
これまで書かないようにしてきました。
でも、大工に対する誤解が多いので、
一度、ちゃんと伝えておこうと思いました。
大工は、広告宣伝や営業にお金を回せていませんし
少人数で仕事していますので、人件費も高くありません。
金額相応の、いい仕事をする自信もあります。
メーカーさんが悪いことをしているという話ではありませんよ。
経営方針が違うだけの話です。
女性の化粧品のことでも
よく話題になっていることですよね。
CMに素敵な女優さんが出ているということは
それだけ、お金が動いているということです。
確かに、基礎や構造など、
大工として、絶対に節約できないことはあります。
一本もんを使うなど、材木の素材そのものを生かして
構造を造っていきますので、手間がかかります。
とはいえ、決してムダなお金を上乗せしているのではありません。
人にも、地球(山林)に優しい
日本家屋の従来工法を、
これからも提供していきたいと考えていることを
お伝えしておきたいと思います。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
昨日は、37.8度まで熱が出てしまい、
半日ダウン・・・
今日も、熱っぽかったんですが、しっかり仕事をした棟梁です。
さて、匠が物申すも今回で28回目になります。
いろんな方の考え方がありますが、
棟梁の思った事を綴っているので、ご理解して頂きたいと思っています。、
*大工に頼むと、工期が長い分だけ高いのでは?
アンケートに答えていただきまして
本当にありがとうございました。
おかげさまで、個人が収集するにしては
たくさんの回答が集まったようです。
そして、わかったのは、
やはり「日本家屋は高いのではないか?」
という印象をお持ちの方が多いことでした。
豊橋は、37万都市です。
僕は10,000分の1である37人のお客様がいらっしゃれば
生計が成り立つので、それで充分だと考えています。
欲張るつもりはありません。
とはいえ、まだ、37人には達していませんが。
残念ながら、昨今では、みなさんの感覚が、
「家を建てる」よりも「家を買う」になっています。
そして、不況の影響もあり、家を選ぶ基準として
「価格」を挙げる方も多いのが現実です。
確かに、価格は気になりますよね。
「工期が長い分、高くなるのではないか」
と言われることがありますが、それはありません。
例えば、3000万円で家を建てるとします。
ハウスメーカーで建てるなら、
確かに、工期3ヶ月でできるでしょう。
でも、本社利益、営業所経費、人件費、広告宣伝費、開発費等
などかかりますので
純粋に、現場で動く大工の人件費と、材料費だけに
支払われている金額ではないわけです。
大工が、3000万円いただいて建てるなら
確かに、工期は8ヶ月かかるかもしれませんが、
それは、それ相応の肯定を経ている理由があるだけです。
金額については、材料費と、人件費だけで
そのほとんどを占めていることになります。
その金額いっぱいの仕事をさせていただくことができるのです。
僕としては、それで充分です。
このカラクリに触れることは御法度だろうと
これまで書かないようにしてきました。
でも、大工に対する誤解が多いので、
一度、ちゃんと伝えておこうと思いました。
大工は、広告宣伝や営業にお金を回せていませんし
少人数で仕事していますので、人件費も高くありません。
金額相応の、いい仕事をする自信もあります。
メーカーさんが悪いことをしているという話ではありませんよ。
経営方針が違うだけの話です。
女性の化粧品のことでも
よく話題になっていることですよね。
CMに素敵な女優さんが出ているということは
それだけ、お金が動いているということです。
確かに、基礎や構造など、
大工として、絶対に節約できないことはあります。
一本もんを使うなど、材木の素材そのものを生かして
構造を造っていきますので、手間がかかります。
とはいえ、決してムダなお金を上乗せしているのではありません。
人にも、地球(山林)に優しい
日本家屋の従来工法を、
これからも提供していきたいと考えていることを
お伝えしておきたいと思います。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2014年09月03日
第26弾「匠が物申す」アンケート編
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
リフォームの現場も残す所、玄関ホールのみ!
ラストスパートで頑張る棟梁です。
さて、「匠が物申す」も第26回目を迎えました。
ここで、記事の最後にアンケートを付けました。
9月の末のお申込みで、抽選で20人の方に、
加藤建築オリジナルタオルとパンフレットを、
送らさせて頂きたいと思いますので、
お気軽にアンケートの方をどうぞご覧ください。

【和モダンなデザインにも挑戦してみたい】
大工の棟梁も、進化し続けなければいけない。
僕は、そう思いながら、
勉強をしたり、技術を磨いたりしてきました。
この歳になって、『和モダン』のデザインにも
挑戦してみようかと思うようになったのです。
日々、勉強ですよね!
伝統的な和風建築は、装飾が派手なものです。
10年前までは、施主さんのご希望としても
「いつかは入母屋造りを」という想いがあったのです。
立派な家を建てることは
施主さんにとって自慢なところでもあり
僕ら大工にとっては「技術」を見せる場でもあります。
でも、お金の掛け方、施主さんの好みなど
時代は、どんどん変わってきています。
そのニーズに合わせて
僕らも進化し続けていく方法を
考えなければいけないところに来ているようです。
とはいえ、プレカット工法の材木を使った
シンプルな家を建てるつもりは、やっぱりありません。
一本ものを使ったり、手刻みで組んでいったりと
人と森林に優しい伝統工法を
後の世代に伝える使命も、やはり感じているのです。
これまでの伝統的な和風建築の良さを残しつつ
若い世代のニーズに合うデザインを取り入れるという
新しい道への枝葉を広げたいのです。
『和モダン』と呼ばれる
シンプルな和風建築のデザインを
これから少しずつ学んでいきたいと思っています。
そこで、参考までにアンケートを取らせてください。
日本家屋、和風建築について
みなさんがお持ちのイメージなどについてのアンケートです。
自由記述の少ないカンタンな内容ですので
ぜひ、ご協力ください。
【アンケートはこちらのフォームから】
https://docs.google.com/forms/d/1wwua9El8qjJ99VrtBmh2bdhWMDfyhdMBFFUS5L7BHTY/viewform
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
リフォームの現場も残す所、玄関ホールのみ!
ラストスパートで頑張る棟梁です。
さて、「匠が物申す」も第26回目を迎えました。
ここで、記事の最後にアンケートを付けました。
9月の末のお申込みで、抽選で20人の方に、
加藤建築オリジナルタオルとパンフレットを、
送らさせて頂きたいと思いますので、
お気軽にアンケートの方をどうぞご覧ください。
【和モダンなデザインにも挑戦してみたい】
大工の棟梁も、進化し続けなければいけない。
僕は、そう思いながら、
勉強をしたり、技術を磨いたりしてきました。
この歳になって、『和モダン』のデザインにも
挑戦してみようかと思うようになったのです。
日々、勉強ですよね!
伝統的な和風建築は、装飾が派手なものです。
10年前までは、施主さんのご希望としても
「いつかは入母屋造りを」という想いがあったのです。
立派な家を建てることは
施主さんにとって自慢なところでもあり
僕ら大工にとっては「技術」を見せる場でもあります。
でも、お金の掛け方、施主さんの好みなど
時代は、どんどん変わってきています。
そのニーズに合わせて
僕らも進化し続けていく方法を
考えなければいけないところに来ているようです。
とはいえ、プレカット工法の材木を使った
シンプルな家を建てるつもりは、やっぱりありません。
一本ものを使ったり、手刻みで組んでいったりと
人と森林に優しい伝統工法を
後の世代に伝える使命も、やはり感じているのです。
これまでの伝統的な和風建築の良さを残しつつ
若い世代のニーズに合うデザインを取り入れるという
新しい道への枝葉を広げたいのです。
『和モダン』と呼ばれる
シンプルな和風建築のデザインを
これから少しずつ学んでいきたいと思っています。
そこで、参考までにアンケートを取らせてください。
日本家屋、和風建築について
みなさんがお持ちのイメージなどについてのアンケートです。
自由記述の少ないカンタンな内容ですので
ぜひ、ご協力ください。
【アンケートはこちらのフォームから】
https://docs.google.com/forms/d/1wwua9El8qjJ99VrtBmh2bdhWMDfyhdMBFFUS5L7BHTY/viewform
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2014年08月08日
匠が物申す第25弾
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
台風の進路が心配ですが、
十分な警戒をして頂きたいと思っている棟梁です。
匠が物申すも25回目を迎える事になりました。
今回はいろんな誤解を解消したくて少し踏み込んで、
綴って見ました。
色々なご意見があるかも分かりませんが、
棟梁の普段からの思いですので、ご了承して頂きたいと思います。
【家屋のお医者さんです】
「加藤さんに、どんなことをやってもらえるのかわからない」
と、よく言われます。
何でもやります(笑)。
棟梁に頼むよりも、職人に直接頼んだほうが安いんじゃないか
と思っている人がいるようです。
僕が手数料を取ると思っておられる。
はっきり申し上げますが、
僕は「ちょっと気になるところを見て欲しい」
という相談については、お金をいただいていません。
その代わり、僕の時間の都合に合わせてもらって
「ついでのタイミング」に見せてもらうんです。
棟梁って、この出立ちのせいか、怖いと思われがちですが、
実は、困ってる人に親身になるもんなんですよ。
棟梁は、頼られることに弱いんです(笑)。

■相談はもちろん業者の手配も無料です
業者に直接頼んだほうが安いと思っている人は
商売の鉄則をご存じないのかもしれません。
仮に、業者さんが、棟梁である僕に出すよりも
安い請求書をお客さんに出したとします。
もしも、棟梁にバレたら、仕事がもらえないはずですよ。
それが、商売の法則です。
ちょっと相談するだけでもお金を取る
業者を頼んでくれるとしても手数料を取る
というのが、どこから持ち始めた認識かわかりません。
珈琲一杯出してくれれば、僕は業者さんを手配します(笑)。
現代は、何でも分業の時代なので、
専門家じゃないとわからないと思っている方も多いようです。
でも、僕は家造りの全体を見渡して統括している立場ですので
不具合を見るときも、部分じゃなく全体を見ます。
それぞれに頼むよりも、全体を見渡せる棟梁に頼めば、どのぐらいの修理が必要なのか、何が原因なのか見られるんです。
つまり、僕に依頼するとこんなメリットがあります。
・全体を見たうえで原因や必要な修理を把握できる
・僕でできることなら僕のほうで修理を終える
・業者がやった後の仕事ぶりも棟梁としてチェックする
例えば、「大工はリフォームできない」
と思っている方も、いらっしゃるようです。
でも、大工は家をイチから作るわけなので、
もちろんリフォームもできるんですよ。
僕は、トタンも貼れるし、瓦も張れるし、
サイディング(外壁)もできます。
極端な話、水道工事だってやろうと思えばできる。
やらないだけです(笑)。
できないと思われているのも、ちょっと悔しいですよね。
■加藤建築で建てた家じゃなくても診にいきます!
僕は、「街の家のお医者さん」になりたいんですね。
建物の主治医みたいなものです。
例えば、先日こんな相談がありました。
「雨漏りするんですが
その原因を追求してもらうことってできますか?」
と聞かれたんですね。
答えはもちろん、「はい、できます」ですよ(笑)。
加藤建築ではない
一般のハウスメーカーさんで建てた家に依頼されて
先日も、外壁の修理に行きました。
その家で、上記のような質問を受けました。
お風呂の窓の下のほうの基礎の部分にシミが出るんです。
でも、床下にもぐってみても、
点検口を開けてみても何ともない。
そこで、ユニットバスを組む業者さんに相談したところ、
「窓枠のコーキング(※)が切れているかもしれない」と。
確かにコーキングが切れていたんです。
※コーキング:窓枠周りのすき間に詰めるパテ状の充填材、もしくは、それを詰めること
でも、24時間換気の家なので、換気扇はかけっぱなしで、
パネルは乾いているし、見た目には確かに換気できていました。
ただ、換気扇をつけているからと、
どうやらお風呂の窓をあまり開けていないらしいんです。
窓の網戸を外して中を見たら、15時ごろなのに、
露でびしょびしょに濡れていました。
そこで
「家にいるときだけでも、風呂場の窓を開けておく」
ということを提案して、様子を見てもらいました。
すると、シミが出なくなりました!
シミが出やすいのは冬場ということだったので、
冬場も同じように試してみないと何とも言えませんが、
それまで持つなら、ラッキーですよね。
とりあえずは何も修理をしなくて済みました。
これも、もし、わからない人に頼んだなら、
外壁からすべて取ってしまっていたかもしれませんし
そうなると余計な金額や日数がかかってしまいます。
ついでに、給湯器の取替についても相談されました。
他社さんの見積もりでは最新の機種で書かれていて
値段がすごく高かったのです。
でも、その地域は海が近く、塩害があります。
どれほど良い機種を使おうと、いずれにしても
10年ごとに買い替えなければならないとわかっていたので、
ワンランク下の安い機種を提案することができました。
さらに、トイレの水漏れの相談をしたら
やはりガスショップの人には「便器を変えたほうがいい」
と言われ、15万円ほどの見積もりだったようえす。
そこでまた、「加藤さんどう思う?」と聞かれたので
また診にいってきました。
便器には問題無さそうだったのですが
部品を交換する必要がありそうでした。
便器の入れ替えが必要な場合も、
僕の知り合いの業者に頼めますと伝えたら
「業者さんを呼んで欲しい」と頼まれ手配しました。
すると、やっぱり部品と工賃だけで2万円で済んだんです。
水道の取り付け部分の劣化が始まっていただけでした。
こんなふうに、どんなことでも、
相談してもらえば対応できます!
加藤建築が建てた家については、
毎年、お盆と正月には点検に伺っています。
その代わり、これも僕が仕事の合間に行くので、
在宅かどうかは確認していません。
不在なら、タオルだけ置いてくるんです。
「あ、加藤さん来てくれたんだな」と思ってもらったら、
また何かあれば電話してくれるし、
急ぎじゃなければ、半年後まで待ってくれたらいいわけです。
棟梁をうまく使ってもらったら、
家を長持ちさせることができるんです。
京都の町家なんかも、そうやって残ってきたはずなんです。
気軽に、声をかけてくださいね。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
台風の進路が心配ですが、
十分な警戒をして頂きたいと思っている棟梁です。
匠が物申すも25回目を迎える事になりました。
今回はいろんな誤解を解消したくて少し踏み込んで、
綴って見ました。
色々なご意見があるかも分かりませんが、
棟梁の普段からの思いですので、ご了承して頂きたいと思います。
【家屋のお医者さんです】
「加藤さんに、どんなことをやってもらえるのかわからない」
と、よく言われます。
何でもやります(笑)。
棟梁に頼むよりも、職人に直接頼んだほうが安いんじゃないか
と思っている人がいるようです。
僕が手数料を取ると思っておられる。
はっきり申し上げますが、
僕は「ちょっと気になるところを見て欲しい」
という相談については、お金をいただいていません。
その代わり、僕の時間の都合に合わせてもらって
「ついでのタイミング」に見せてもらうんです。
棟梁って、この出立ちのせいか、怖いと思われがちですが、
実は、困ってる人に親身になるもんなんですよ。
棟梁は、頼られることに弱いんです(笑)。

■相談はもちろん業者の手配も無料です
業者に直接頼んだほうが安いと思っている人は
商売の鉄則をご存じないのかもしれません。
仮に、業者さんが、棟梁である僕に出すよりも
安い請求書をお客さんに出したとします。
もしも、棟梁にバレたら、仕事がもらえないはずですよ。
それが、商売の法則です。
ちょっと相談するだけでもお金を取る
業者を頼んでくれるとしても手数料を取る
というのが、どこから持ち始めた認識かわかりません。
珈琲一杯出してくれれば、僕は業者さんを手配します(笑)。
現代は、何でも分業の時代なので、
専門家じゃないとわからないと思っている方も多いようです。
でも、僕は家造りの全体を見渡して統括している立場ですので
不具合を見るときも、部分じゃなく全体を見ます。
それぞれに頼むよりも、全体を見渡せる棟梁に頼めば、どのぐらいの修理が必要なのか、何が原因なのか見られるんです。
つまり、僕に依頼するとこんなメリットがあります。
・全体を見たうえで原因や必要な修理を把握できる
・僕でできることなら僕のほうで修理を終える
・業者がやった後の仕事ぶりも棟梁としてチェックする
例えば、「大工はリフォームできない」
と思っている方も、いらっしゃるようです。
でも、大工は家をイチから作るわけなので、
もちろんリフォームもできるんですよ。
僕は、トタンも貼れるし、瓦も張れるし、
サイディング(外壁)もできます。
極端な話、水道工事だってやろうと思えばできる。
やらないだけです(笑)。
できないと思われているのも、ちょっと悔しいですよね。
■加藤建築で建てた家じゃなくても診にいきます!
僕は、「街の家のお医者さん」になりたいんですね。
建物の主治医みたいなものです。
例えば、先日こんな相談がありました。
「雨漏りするんですが
その原因を追求してもらうことってできますか?」
と聞かれたんですね。
答えはもちろん、「はい、できます」ですよ(笑)。
加藤建築ではない
一般のハウスメーカーさんで建てた家に依頼されて
先日も、外壁の修理に行きました。
その家で、上記のような質問を受けました。
お風呂の窓の下のほうの基礎の部分にシミが出るんです。
でも、床下にもぐってみても、
点検口を開けてみても何ともない。
そこで、ユニットバスを組む業者さんに相談したところ、
「窓枠のコーキング(※)が切れているかもしれない」と。
確かにコーキングが切れていたんです。
※コーキング:窓枠周りのすき間に詰めるパテ状の充填材、もしくは、それを詰めること
でも、24時間換気の家なので、換気扇はかけっぱなしで、
パネルは乾いているし、見た目には確かに換気できていました。
ただ、換気扇をつけているからと、
どうやらお風呂の窓をあまり開けていないらしいんです。
窓の網戸を外して中を見たら、15時ごろなのに、
露でびしょびしょに濡れていました。
そこで
「家にいるときだけでも、風呂場の窓を開けておく」
ということを提案して、様子を見てもらいました。
すると、シミが出なくなりました!
シミが出やすいのは冬場ということだったので、
冬場も同じように試してみないと何とも言えませんが、
それまで持つなら、ラッキーですよね。
とりあえずは何も修理をしなくて済みました。
これも、もし、わからない人に頼んだなら、
外壁からすべて取ってしまっていたかもしれませんし
そうなると余計な金額や日数がかかってしまいます。
ついでに、給湯器の取替についても相談されました。
他社さんの見積もりでは最新の機種で書かれていて
値段がすごく高かったのです。
でも、その地域は海が近く、塩害があります。
どれほど良い機種を使おうと、いずれにしても
10年ごとに買い替えなければならないとわかっていたので、
ワンランク下の安い機種を提案することができました。
さらに、トイレの水漏れの相談をしたら
やはりガスショップの人には「便器を変えたほうがいい」
と言われ、15万円ほどの見積もりだったようえす。
そこでまた、「加藤さんどう思う?」と聞かれたので
また診にいってきました。
便器には問題無さそうだったのですが
部品を交換する必要がありそうでした。
便器の入れ替えが必要な場合も、
僕の知り合いの業者に頼めますと伝えたら
「業者さんを呼んで欲しい」と頼まれ手配しました。
すると、やっぱり部品と工賃だけで2万円で済んだんです。
水道の取り付け部分の劣化が始まっていただけでした。
こんなふうに、どんなことでも、
相談してもらえば対応できます!
加藤建築が建てた家については、
毎年、お盆と正月には点検に伺っています。
その代わり、これも僕が仕事の合間に行くので、
在宅かどうかは確認していません。
不在なら、タオルだけ置いてくるんです。
「あ、加藤さん来てくれたんだな」と思ってもらったら、
また何かあれば電話してくれるし、
急ぎじゃなければ、半年後まで待ってくれたらいいわけです。
棟梁をうまく使ってもらったら、
家を長持ちさせることができるんです。
京都の町家なんかも、そうやって残ってきたはずなんです。
気軽に、声をかけてくださいね。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2014年07月13日
匠が物申す第24弾
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
午前中は、外仕事が出来ましたが、雨が降ってきて、
仕事をするのを断念した棟梁です。
さて「匠が物申す」も、
第24回目を掲載する事が出来ました。
時代の流れで、知らなくてはいけない事がだんだんと、
忘れ去られて行く、そんな風になって来た事がとても残念です。
色々なご意見はあると思いますが、棟梁の思いなのでご了承ください。
【畳のお話】
今回は、畳の話をします。
畳の専門家ではないのですが
「どうして畳を虫干しするの?」と質問をいただいたので。

■い草と藁は湿度を調整してくれる
国民的人気アニメの『サザエさん』なんかでも
庭に、畳を立てかけて干してあるシーンを
見たことがある方もいらっしゃると思います。
虫干しするのは、畳の
ダニ、カビ、埃などの対策のためなんです。
天気のいい日に、3~4時間干して、最後に、叩きます。
畳にはいくつか種類があります。
「本床(ほんどこ)」と呼ばれる畳は
約6cmほどの厚みがあり、中には藁(わら)が使われています。
い草と藁が、湿度を調整してくれるので
断然、本床がお勧めなんですが、手入れが必要です。
最近は、どんどん薄くて軽い安い畳が増えてきています。
段ボールの圧縮材でウレタンマットを挟んだものに
い草を敷いてあるだけのものや
い草の代わりにビニールを使用しているものもあります。
気軽に使えますが、安いものは、人が歩く程度の摩擦でも
すり減ってくるという、難点もあるようです。
聞くところに寄ると、い草の染め方も違うようです。
青いほうが高級感があるように見えるため
あえて青く染めるという話も聞きます。
本床が避けられるようになったのは、
畳はダニやカビの温床という
悪い印象が持たれるようになったためです。
ダニやカビが生えるのは、建築方法が変わってきたこと、
年に2回ほどの虫干しをしなくなったこと、
現代は掃除をする回数も減ってきたことなどが原因です。
昔は、畳の掃除といえば、お茶がらを撒いておいて
埃を吸わせてから拭き掃除をしたりもしていました。
そういうやり方も知らない人が増えていますし
掃除機をかける回数も減ってきているようです。
だから、ダニが発生しやすいんですね。
畳屋さんとしても、ちゃんと手入れしてもらえないなら
安いものを勧めておいて、数年後、一式すべて変えればいい
と、考えているのかもしれません。
■日本から、い草や藁が消えていっている
今、い草の生産については、
80%以上、中国に頼っていると言われています。
自然のなかで育った、太さの違うい草を揃えるのが大変で
一畳10万円という最高級の畳もあるようです。
本床の畳は、手織りなので時間もかかります。
一枚作るのに、二日ぐらいかかると聞いたこともあります。
また、昔は、藁が日本中に普通にありました。
お米を収穫するときに、昔は稲を手で刈り取って
「はざ掛け」などと呼ばれ、天日干しにするのが習わしでした。
でも、今は、コンバインなどの大型機械で刈ってしまいます。
はざ掛けをすると、干している間に
藁に溜まっている栄養素が、米粒にまで行き渡り
甘み・うま味・粘りが増す、と言われています。
でも、はざ掛けには、人手がいりますし、
天候に左右されてしまうので、最近は見かけなくなったんですね。
そうして、天日干しにした藁は
藁床、土壁、畑の畝にかける敷き藁、草鞋、しめ縄など
たくさんの使い道がありました。
生活のなかで「循環」させていたんですね。
藁の使い道である「土壁」を使った家も減り
洋室が増えたことで、畳も減るなど
どんどん藁を使う機会がなくなってきて
藁自体も、減っていったんですね。悪循環です。
昔の家は広さもあり、庭先に畳を干す場所もあった。
今は、その場所もなくなってきていますし
核家族化で、一緒に暮らす人数が減ってきたのも
虫干しをしなくなった原因かもしれませんね。
家屋のことも含め、とにかく、あらゆることに於いて
「手入れをして長持ちさせる」という感覚が
なくなってきているのを感じます。
こうして日本の文化が消えていくのは
とても残念なことだと思います。
土壁などといっしょに、最近は少し畳の良さが
見直されつつあると言われていますが
そうであればいいなと、僕は思っています。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
午前中は、外仕事が出来ましたが、雨が降ってきて、
仕事をするのを断念した棟梁です。
さて「匠が物申す」も、
第24回目を掲載する事が出来ました。
時代の流れで、知らなくてはいけない事がだんだんと、
忘れ去られて行く、そんな風になって来た事がとても残念です。
色々なご意見はあると思いますが、棟梁の思いなのでご了承ください。
【畳のお話】
今回は、畳の話をします。
畳の専門家ではないのですが
「どうして畳を虫干しするの?」と質問をいただいたので。

■い草と藁は湿度を調整してくれる
国民的人気アニメの『サザエさん』なんかでも
庭に、畳を立てかけて干してあるシーンを
見たことがある方もいらっしゃると思います。
虫干しするのは、畳の
ダニ、カビ、埃などの対策のためなんです。
天気のいい日に、3~4時間干して、最後に、叩きます。
畳にはいくつか種類があります。
「本床(ほんどこ)」と呼ばれる畳は
約6cmほどの厚みがあり、中には藁(わら)が使われています。
い草と藁が、湿度を調整してくれるので
断然、本床がお勧めなんですが、手入れが必要です。
最近は、どんどん薄くて軽い安い畳が増えてきています。
段ボールの圧縮材でウレタンマットを挟んだものに
い草を敷いてあるだけのものや
い草の代わりにビニールを使用しているものもあります。
気軽に使えますが、安いものは、人が歩く程度の摩擦でも
すり減ってくるという、難点もあるようです。
聞くところに寄ると、い草の染め方も違うようです。
青いほうが高級感があるように見えるため
あえて青く染めるという話も聞きます。
本床が避けられるようになったのは、
畳はダニやカビの温床という
悪い印象が持たれるようになったためです。
ダニやカビが生えるのは、建築方法が変わってきたこと、
年に2回ほどの虫干しをしなくなったこと、
現代は掃除をする回数も減ってきたことなどが原因です。
昔は、畳の掃除といえば、お茶がらを撒いておいて
埃を吸わせてから拭き掃除をしたりもしていました。
そういうやり方も知らない人が増えていますし
掃除機をかける回数も減ってきているようです。
だから、ダニが発生しやすいんですね。
畳屋さんとしても、ちゃんと手入れしてもらえないなら
安いものを勧めておいて、数年後、一式すべて変えればいい
と、考えているのかもしれません。
■日本から、い草や藁が消えていっている
今、い草の生産については、
80%以上、中国に頼っていると言われています。
自然のなかで育った、太さの違うい草を揃えるのが大変で
一畳10万円という最高級の畳もあるようです。
本床の畳は、手織りなので時間もかかります。
一枚作るのに、二日ぐらいかかると聞いたこともあります。
また、昔は、藁が日本中に普通にありました。
お米を収穫するときに、昔は稲を手で刈り取って
「はざ掛け」などと呼ばれ、天日干しにするのが習わしでした。
でも、今は、コンバインなどの大型機械で刈ってしまいます。
はざ掛けをすると、干している間に
藁に溜まっている栄養素が、米粒にまで行き渡り
甘み・うま味・粘りが増す、と言われています。
でも、はざ掛けには、人手がいりますし、
天候に左右されてしまうので、最近は見かけなくなったんですね。
そうして、天日干しにした藁は
藁床、土壁、畑の畝にかける敷き藁、草鞋、しめ縄など
たくさんの使い道がありました。
生活のなかで「循環」させていたんですね。
藁の使い道である「土壁」を使った家も減り
洋室が増えたことで、畳も減るなど
どんどん藁を使う機会がなくなってきて
藁自体も、減っていったんですね。悪循環です。
昔の家は広さもあり、庭先に畳を干す場所もあった。
今は、その場所もなくなってきていますし
核家族化で、一緒に暮らす人数が減ってきたのも
虫干しをしなくなった原因かもしれませんね。
家屋のことも含め、とにかく、あらゆることに於いて
「手入れをして長持ちさせる」という感覚が
なくなってきているのを感じます。
こうして日本の文化が消えていくのは
とても残念なことだと思います。
土壁などといっしょに、最近は少し畳の良さが
見直されつつあると言われていますが
そうであればいいなと、僕は思っています。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2014年05月14日
匠がもの申す第23弾 「宮大工の手伝い」
宮大工の手伝い ~「加藤くん!」と呼ばれて~
ずっと憧れていた、宮大工の仕事の
手伝いに行くことができました!

内閣総理大臣賞にも輝いた
吉田藩の最後の棟梁の最後のお弟子さんでもいらっしゃる
今は亡き宮大工、阿部幸次郎さんの
阿部工務店さんです。
親父が一級の技能検定を取る時に、
阿部幸次郎先生に教えてもらったご縁もあり、
ずっと憧れていました。
今回は、彫刻士の仲間が紹介してくれ
10日間の約束で、働かせてもらいました。
「よろしくお願いします!」と挨拶して
棟梁に「加藤くん!」と呼ばれながら仕事しました。
新米の若い衆のころを思い出しましたねぇ(笑)。
僕がお手伝いさせてもらったのは、
とある「お寺の本堂」の建て替え工事。
「これがホンモノだ!」と思いましたね。
びっくりするぐらいの仕事ぶりなんですが、
それでも「簡略化している」のだそうです。
床も、屋根も、住宅と違って高さがありますし、
木材も、全体的に太くて長いんですよ。
それらが、5mmのズレもなく、
すべてが綺麗に収まっていくのは「圧巻」です!
例えば、通し柱でも、僕らが「女大黒」として
使っているの太さ(7寸=21cm)のものを使っていました。
幅21cm、高さ12cmの土台の上に柱を立てていき、
その60cmぐらい上がったところに、
「足固め」を張り、その上に床を張ります。
つまり、基礎から1mほど上がったところが床になるので
やっぱり民家と違って、高いですね。
それなのに、筋交いも何も無しに建っていくんですよ。
きれいに、すぼすぼと柱が入っていくのを見ると
「すごい!」の一言です!
丸桁(がぎょう)という垂木を支える材料は檜で
一番大きな中桁など、長さ12mほどもあるんです。
太さなんて、末は50cmぐらい、根っこは90cmほど。


「日本に、まだ、こんな大きな木があったか!」と驚きました!
岐阜の奥のほうにある木だそうです。
小屋組みを組んだ後、棟のてっぺんに登らせてもらいましたが
25tレッカー車が、ミニカーみたいに見えました。

6mの高さの初重張りのところを
歩いていけと言われた時には、
さすがに「無理です!」と言ってしまいました。
でも、だんだん慣れてくるもので
「加藤くん大丈夫か?」と言われて
「はい、がんばってみます」と歩いてみました。

あれだけの大きさのものを
どうすれば、きっちり刻めるのかっていうのは
僕らプロから見ても、本当に驚くばかりです。
あれが「本物を造る人たち」なんでしょうね!
野組の方法は、恐らく基本は同じはずです。
ただ、「寸法の出し方」については企業秘密なんですよ。

社寺建築には、きっと独特の方法があるんだと思います。
そこは、教えてもらえませんのでね(笑)。
阿部工務店さんの現在の棟梁は、
細身で小さくて、飛ぶように歩くような身軽な棟梁ですが
知識と経験と度胸は、やっぱりピカイチ!
僕は、10日間の契約で8日ほどしかできなかったのですが、
最終日に、棟梁に「加藤くん! 配付墨木を取り付けておいて」と、
いきなり言われました。
「できるわけないじゃないですか!」と、驚いて答えると
「大丈夫大丈夫! 加藤くんならできる!
グランプリに行ったことある人が、何を言うとる?」
なんて言いながら、本当に任せてくれるんですよ。
時間はかかったとしても、絶対にやりきるだろうと
信じてくれてるんですよね。

最初はなかなか、差し込めなくてよく見ると
ほず(ほぞ)穴を、わざとに小さく作ってありました。
ちゃんとあてがって寸法を取らないとダメなんですね。
それを4本すべて、寸法とってつけていたら
14時から始めて、夜までかかってしまいました。

棟梁には「ちゃんとできとるじゃん!」と言われ、
その後、社長にも、今後も手伝いに来てもらえないかと
言ってもらいました。
行きたかったものの、僕も本業があるのでお断りしましたが、
宮大工さんに認めてもらえるのは、本当に嬉しいことです。
こんなふうに、僕もまだまだ、
常に、勉強をしつつ、腕を鍛えています。
棟梁
新先輩レポートインタビュー(お客様の声)
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
ずっと憧れていた、宮大工の仕事の
手伝いに行くことができました!
内閣総理大臣賞にも輝いた
吉田藩の最後の棟梁の最後のお弟子さんでもいらっしゃる
今は亡き宮大工、阿部幸次郎さんの
阿部工務店さんです。
親父が一級の技能検定を取る時に、
阿部幸次郎先生に教えてもらったご縁もあり、
ずっと憧れていました。
今回は、彫刻士の仲間が紹介してくれ
10日間の約束で、働かせてもらいました。
「よろしくお願いします!」と挨拶して
棟梁に「加藤くん!」と呼ばれながら仕事しました。
新米の若い衆のころを思い出しましたねぇ(笑)。
僕がお手伝いさせてもらったのは、
とある「お寺の本堂」の建て替え工事。
「これがホンモノだ!」と思いましたね。
びっくりするぐらいの仕事ぶりなんですが、
それでも「簡略化している」のだそうです。
床も、屋根も、住宅と違って高さがありますし、
木材も、全体的に太くて長いんですよ。
それらが、5mmのズレもなく、
すべてが綺麗に収まっていくのは「圧巻」です!
例えば、通し柱でも、僕らが「女大黒」として
使っているの太さ(7寸=21cm)のものを使っていました。
幅21cm、高さ12cmの土台の上に柱を立てていき、
その60cmぐらい上がったところに、
「足固め」を張り、その上に床を張ります。
つまり、基礎から1mほど上がったところが床になるので
やっぱり民家と違って、高いですね。
それなのに、筋交いも何も無しに建っていくんですよ。
きれいに、すぼすぼと柱が入っていくのを見ると
「すごい!」の一言です!
丸桁(がぎょう)という垂木を支える材料は檜で
一番大きな中桁など、長さ12mほどもあるんです。
太さなんて、末は50cmぐらい、根っこは90cmほど。

「日本に、まだ、こんな大きな木があったか!」と驚きました!
岐阜の奥のほうにある木だそうです。
小屋組みを組んだ後、棟のてっぺんに登らせてもらいましたが
25tレッカー車が、ミニカーみたいに見えました。

6mの高さの初重張りのところを
歩いていけと言われた時には、
さすがに「無理です!」と言ってしまいました。
でも、だんだん慣れてくるもので
「加藤くん大丈夫か?」と言われて
「はい、がんばってみます」と歩いてみました。
あれだけの大きさのものを
どうすれば、きっちり刻めるのかっていうのは
僕らプロから見ても、本当に驚くばかりです。
あれが「本物を造る人たち」なんでしょうね!
野組の方法は、恐らく基本は同じはずです。
ただ、「寸法の出し方」については企業秘密なんですよ。

社寺建築には、きっと独特の方法があるんだと思います。
そこは、教えてもらえませんのでね(笑)。
阿部工務店さんの現在の棟梁は、
細身で小さくて、飛ぶように歩くような身軽な棟梁ですが
知識と経験と度胸は、やっぱりピカイチ!
僕は、10日間の契約で8日ほどしかできなかったのですが、
最終日に、棟梁に「加藤くん! 配付墨木を取り付けておいて」と、
いきなり言われました。
「できるわけないじゃないですか!」と、驚いて答えると
「大丈夫大丈夫! 加藤くんならできる!
グランプリに行ったことある人が、何を言うとる?」
なんて言いながら、本当に任せてくれるんですよ。
時間はかかったとしても、絶対にやりきるだろうと
信じてくれてるんですよね。
最初はなかなか、差し込めなくてよく見ると
ほず(ほぞ)穴を、わざとに小さく作ってありました。
ちゃんとあてがって寸法を取らないとダメなんですね。
それを4本すべて、寸法とってつけていたら
14時から始めて、夜までかかってしまいました。
棟梁には「ちゃんとできとるじゃん!」と言われ、
その後、社長にも、今後も手伝いに来てもらえないかと
言ってもらいました。
行きたかったものの、僕も本業があるのでお断りしましたが、
宮大工さんに認めてもらえるのは、本当に嬉しいことです。
こんなふうに、僕もまだまだ、
常に、勉強をしつつ、腕を鍛えています。
棟梁
新先輩レポートインタビュー(お客様の声)
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2014年04月14日
匠がもの申す第22弾「どんな家が建てたいですか?」 ~カタログに無い家~
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
今日も、精一杯やったご褒美は、
先ほどまで(PM9:30)、現場でペンキ屋さんとデートでした(笑)
現場も、いよいよ内覧会を待つのみ!
思い通りの家に仕上がって凄く嬉しく思っています。
そこで、匠がもの申す「第22弾
「どんな家が建てたいですか?」 ~カタログに無い家~
いよいよ、家ができあがってきました。
実は、今回の家、建前まではもちろん僕がやりますが、
内装に関しては、玄関の天板と飾り棚をつけただけ。
唐傘天井を含めて、ほとんど若い衆にやらせています。
階段も、若い衆がやっていますが、
この階段の上の天井が、ちょっと凹んでいます。
なぜだかわかりますか?
実物をちゃんと見てもらえばわかります!

僕は、「苦にならないように造るのが大工」
だと思っています。
「苦にならない」というのは、
「生活していくうえで違和感を感じない」
という意味です。
そのためのアイデアが、いっぱい詰まった家を
僕は、建てています。
今回の家は、本当に楽しい現場でした。
施主さんと、心を合わせて建てていることを
実感しながら造ることができました。
僕の持っている様々な技術と
僕のところにある材料を
惜しみなく、この現場に使ってきました。
この心意気を、わかってもらえる方は
もしかしたら、少ないのかもしれません。
それでも、1000人に1人でもいらっしゃるのなら
その方のためにがんばればいいか
と、僕は思っています。
今の時代。
家を購入するための35年ローンを組むことを
たった、一ヶ月で決めてしまうこともあるそうです。
提案されるがままに、
カタログのなかから、すべてを選ぶ時代。
「自分が、どんな家を建てたいのか」
という、イメージが無い方が多いようです。
僕はいつも「どうしたいの?」って
施主さんに訊くんです。
「カタログにない家造り」と、僕は推奨していますが
でも、みなさんピンとこないらしいんですよね。
カタログにあれば、その中からは選ぶことができる。
でも、無いものに関しては想像ができない。
実際、この現場でも、収納の造作については
「何を収納するのかを考えて」と伝えました。
でも、最初は施主さんも困っておられました。
それはきっと、これまでは
「収納を自由に造れる」という発想がなかったから
だと思います。
押し入れは、まず見積もりするときには、
昔ながらの中段と、天棚だけにしておきます。
でも、「パイプをつけてハンガーをかけたい」
などの施主さんの希望があれば、
僕は、どんどんその願いを叶えていきます。
実際にそれが、現実にできあがっているので
ぜひ、見にきていただきたいです。
与えられたものに対して、
何かを選ぶことはできるんですが
自分からイメージすることって
現代の暮らしには、あまり無いのかもしれません。
レストランに入ってメニューから選ぶという発想ですね。
珈琲を注文する時、ブレンドは何にしますか? 砂糖の量は?
というのが、いわゆる一般的な
メーカーさんなどで建てる場合の方法だとすると、
僕の場合は、一からオリジナルの料理を作る感じです。
昔は、お父さん、お母さんはもちろん、
おじいちゃん、おばあちゃんから
いろいろなことを教わりながら、
家のことを、知っていく機会があったんですね。
おじいちゃんのお抱えの棟梁さんがいれば
その人に何でも相談できたんです。
例えば、京都の町家。
間口が狭くて奥行きがあるので
湿気が溜まりやすいはずなのに
なぜ、あれほど長持ちするのでしょうか。
お抱えの大工さんが、お正月などに一軒一軒回ってきて
家を見てくれるんですよ。
「どうですか?」と、毎年見にきては
必要ならば修理して直していく。
メンテナンスをするから長持ちするんですね。
信頼できる棟梁さんとの毎年のおつきあいだから、
どこをどう修理するかはもちろん
請求金額まで、お任せだったようです。
それだけの、信頼関係があったんですね。
大工さんは、新築の家を造りつつ、
修理やリフォームもしつつ、
年間を通して仕事があったということです。
大工の仕事があれば、左官さん、建具屋さんなど
建築に関わる、さまざまな仕事も回っていたんです。
そして、山の木々も循環します。
※「循環」については過去の記事もチェックしてみてください
http://kinoie.dosugoi.net/e433134.html
思い描いた通りの
丈夫で基礎がしっかりした家を建てて
メンテナンスしながら長持ちさせる。
そんな、棟梁と施主さんが心を合わせて造る
従来工法の日本家屋。
この機会に、ゆっくり見学に来てみてください。
4月19日(土)、20日(日)に
見学会をします。
将来、「こんな家が建てたい!」のイメージが
少し膨らむかもしれませんよ!
木の香りや、明るい光や風を
ぜひ、実際に感じてみてくださいね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
新先輩レポートインタビュー
内覧会のご案内
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
今日も、精一杯やったご褒美は、
先ほどまで(PM9:30)、現場でペンキ屋さんとデートでした(笑)
現場も、いよいよ内覧会を待つのみ!
思い通りの家に仕上がって凄く嬉しく思っています。
そこで、匠がもの申す「第22弾
「どんな家が建てたいですか?」 ~カタログに無い家~
いよいよ、家ができあがってきました。
実は、今回の家、建前まではもちろん僕がやりますが、
内装に関しては、玄関の天板と飾り棚をつけただけ。
唐傘天井を含めて、ほとんど若い衆にやらせています。
階段も、若い衆がやっていますが、
この階段の上の天井が、ちょっと凹んでいます。
なぜだかわかりますか?
実物をちゃんと見てもらえばわかります!

僕は、「苦にならないように造るのが大工」
だと思っています。
「苦にならない」というのは、
「生活していくうえで違和感を感じない」
という意味です。
そのためのアイデアが、いっぱい詰まった家を
僕は、建てています。
今回の家は、本当に楽しい現場でした。
施主さんと、心を合わせて建てていることを
実感しながら造ることができました。
僕の持っている様々な技術と
僕のところにある材料を
惜しみなく、この現場に使ってきました。
この心意気を、わかってもらえる方は
もしかしたら、少ないのかもしれません。
それでも、1000人に1人でもいらっしゃるのなら
その方のためにがんばればいいか
と、僕は思っています。
今の時代。
家を購入するための35年ローンを組むことを
たった、一ヶ月で決めてしまうこともあるそうです。
提案されるがままに、
カタログのなかから、すべてを選ぶ時代。
「自分が、どんな家を建てたいのか」
という、イメージが無い方が多いようです。
僕はいつも「どうしたいの?」って
施主さんに訊くんです。
「カタログにない家造り」と、僕は推奨していますが
でも、みなさんピンとこないらしいんですよね。
カタログにあれば、その中からは選ぶことができる。
でも、無いものに関しては想像ができない。
実際、この現場でも、収納の造作については
「何を収納するのかを考えて」と伝えました。
でも、最初は施主さんも困っておられました。
それはきっと、これまでは
「収納を自由に造れる」という発想がなかったから
だと思います。
押し入れは、まず見積もりするときには、
昔ながらの中段と、天棚だけにしておきます。
でも、「パイプをつけてハンガーをかけたい」
などの施主さんの希望があれば、
僕は、どんどんその願いを叶えていきます。
実際にそれが、現実にできあがっているので
ぜひ、見にきていただきたいです。
与えられたものに対して、
何かを選ぶことはできるんですが
自分からイメージすることって
現代の暮らしには、あまり無いのかもしれません。
レストランに入ってメニューから選ぶという発想ですね。
珈琲を注文する時、ブレンドは何にしますか? 砂糖の量は?
というのが、いわゆる一般的な
メーカーさんなどで建てる場合の方法だとすると、
僕の場合は、一からオリジナルの料理を作る感じです。
昔は、お父さん、お母さんはもちろん、
おじいちゃん、おばあちゃんから
いろいろなことを教わりながら、
家のことを、知っていく機会があったんですね。
おじいちゃんのお抱えの棟梁さんがいれば
その人に何でも相談できたんです。
例えば、京都の町家。
間口が狭くて奥行きがあるので
湿気が溜まりやすいはずなのに
なぜ、あれほど長持ちするのでしょうか。
お抱えの大工さんが、お正月などに一軒一軒回ってきて
家を見てくれるんですよ。
「どうですか?」と、毎年見にきては
必要ならば修理して直していく。
メンテナンスをするから長持ちするんですね。
信頼できる棟梁さんとの毎年のおつきあいだから、
どこをどう修理するかはもちろん
請求金額まで、お任せだったようです。
それだけの、信頼関係があったんですね。
大工さんは、新築の家を造りつつ、
修理やリフォームもしつつ、
年間を通して仕事があったということです。
大工の仕事があれば、左官さん、建具屋さんなど
建築に関わる、さまざまな仕事も回っていたんです。
そして、山の木々も循環します。
※「循環」については過去の記事もチェックしてみてください
http://kinoie.dosugoi.net/e433134.html
思い描いた通りの
丈夫で基礎がしっかりした家を建てて
メンテナンスしながら長持ちさせる。
そんな、棟梁と施主さんが心を合わせて造る
従来工法の日本家屋。
この機会に、ゆっくり見学に来てみてください。
4月19日(土)、20日(日)に
見学会をします。
将来、「こんな家が建てたい!」のイメージが
少し膨らむかもしれませんよ!
木の香りや、明るい光や風を
ぜひ、実際に感じてみてくださいね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
新先輩レポートインタビュー
内覧会のご案内
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2014年03月19日
匠がもの申す 第21弾
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
昨日とはうって変って、いいお天気・・・
予定通りコンクリート打ちが終わりホッとしている棟梁です。
匠がもの申すも第21回になりました。
棟梁の思いが大きく、色々な方に色々な思われようが、
あるのか分かりませんが、ご了承ください。

*家はゆっくり建てるものだった
若い世代の人と話していると、
結婚して、いずれマイホームを持ちたいという人もいらっしゃいます。
その場合、マンションになるか、持ち家になるか
好みによって分かれると思います。
もちろん、転勤が多いから賃貸でいいという人もいるでしょう。
「家」を建てたいと思うなら
家のことをしっかり勉強して欲しいと思います。
インターネットのおかげで、勉強しやすくなっていますので、
検索してキーワードを入れれば情報収集できるはずです。
僕のホームページにも、よく「大黒柱」などで
検索して訪問してくださる方がいらっしゃいます。
でも、簡単に検索できるようになった分、
検索上位に上がってくるページの情報を、
鵜呑みにしてしまう危険性もあります。
それも実は、怖いのですが……。
昔の大工さんの仕事は「節分」から始まりました。
節分は、旧暦の正月。
年度の変わり目なので、新しく何かをスタートするのに
良い日だと言われていました。
木を切るのに良い時期があるという話を
以前の記事でも書きました。
12~1月ごろです。
冬は、木が水を吸い上げなくなるため、
虫が入りにくいのです。
夏場に切った木を使うと、必ず虫だらけになるので。
12~1月ごろに切った木を、
皮をむいたり、製材しておいたりしてから
3ヶ月の間、寝かせておきます。
そして、翌年の節分になったら、建て始めるわけです。
こだわりのある方は、建て始めたいと思う時期の
一年前の節分から、木を集め始めていました。
もっと、こだわる方は、10年ぐらいのサイクルで考えます。
暦を見てもらったうえで、
「10年後のこの年に建てると、
家族全員の運気が上がっているから」などと時期を決め
それに向けて準備をしていくわけです。
ゆっくり時間をかけて、家を建てていったのです。
そこまでではなくても、
余裕を持って家作りをして欲しいと思います。
借金返済に一生懸命。
生活に一生懸命。
めまぐるしい暮らしをしていると、
前回お話ししたような「手入れする」ということに
気持ちが向かなくなってしまうのです。
一昔前までは、結婚して、子どもが生まれたころに
夢のマイホームを建てようという話が持ち上がり、
そのために、一生懸命、5~6年かけて
土地を買うための頭金を溜めました。
そして、その間に土地を探したのです。
買った土地は、家を建てるまでは
家庭菜園なんかして、利用しました。
今は、空いた土地は、貸し駐車場にする人もいますが、
そんな考えも、あまり無かったころ、
近所の人や、農家さんなどと交流を深めていきました。
菜園の話などしつつ、いろいろな人とお話をしてくなかで、
知恵のあるおじいちゃんや、おばあちゃんに聞きながら
家の勉強をしていたはずなんです。
その土地の住宅事情を聞きつつ、家について勉強をしてから
やっと、家を建てるということが多かったんです。
情報もゆっくり集め、
お金もしっかり溜めてから建てるので、
失敗も少なかったはずです。
若いときに、無理をして建てると
思っていたように建てることができず、
建て直したり、数年でリフォームしたりすることになってしまう。
世間に煽られて、建ててしまっている人もいるかもしれません。
例えば、「便利」で「安い」という土地には、
やはり、何かしらの事情があることが多いものです。
以前、親戚が土地を買おうとして
「一緒に見て欲しい」と相談されたことがあります。
確かに便利な場所でしたが、100メートル先は運河で
裏は2メートルの絶壁でした。
地震があったら、液状化は間違いないような土地でした。
家のこと、土地のこと、もっと興味を持って
ゆっくり時間をかけて勉強して
家を建てて欲しいものです。
大切な家族が、毎日暮らすための「家」なのですから。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
昨日とはうって変って、いいお天気・・・
予定通りコンクリート打ちが終わりホッとしている棟梁です。
匠がもの申すも第21回になりました。
棟梁の思いが大きく、色々な方に色々な思われようが、
あるのか分かりませんが、ご了承ください。
*家はゆっくり建てるものだった
若い世代の人と話していると、
結婚して、いずれマイホームを持ちたいという人もいらっしゃいます。
その場合、マンションになるか、持ち家になるか
好みによって分かれると思います。
もちろん、転勤が多いから賃貸でいいという人もいるでしょう。
「家」を建てたいと思うなら
家のことをしっかり勉強して欲しいと思います。
インターネットのおかげで、勉強しやすくなっていますので、
検索してキーワードを入れれば情報収集できるはずです。
僕のホームページにも、よく「大黒柱」などで
検索して訪問してくださる方がいらっしゃいます。
でも、簡単に検索できるようになった分、
検索上位に上がってくるページの情報を、
鵜呑みにしてしまう危険性もあります。
それも実は、怖いのですが……。
昔の大工さんの仕事は「節分」から始まりました。
節分は、旧暦の正月。
年度の変わり目なので、新しく何かをスタートするのに
良い日だと言われていました。
木を切るのに良い時期があるという話を
以前の記事でも書きました。
12~1月ごろです。
冬は、木が水を吸い上げなくなるため、
虫が入りにくいのです。
夏場に切った木を使うと、必ず虫だらけになるので。
12~1月ごろに切った木を、
皮をむいたり、製材しておいたりしてから
3ヶ月の間、寝かせておきます。
そして、翌年の節分になったら、建て始めるわけです。
こだわりのある方は、建て始めたいと思う時期の
一年前の節分から、木を集め始めていました。
もっと、こだわる方は、10年ぐらいのサイクルで考えます。
暦を見てもらったうえで、
「10年後のこの年に建てると、
家族全員の運気が上がっているから」などと時期を決め
それに向けて準備をしていくわけです。
ゆっくり時間をかけて、家を建てていったのです。
そこまでではなくても、
余裕を持って家作りをして欲しいと思います。
借金返済に一生懸命。
生活に一生懸命。
めまぐるしい暮らしをしていると、
前回お話ししたような「手入れする」ということに
気持ちが向かなくなってしまうのです。
一昔前までは、結婚して、子どもが生まれたころに
夢のマイホームを建てようという話が持ち上がり、
そのために、一生懸命、5~6年かけて
土地を買うための頭金を溜めました。
そして、その間に土地を探したのです。
買った土地は、家を建てるまでは
家庭菜園なんかして、利用しました。
今は、空いた土地は、貸し駐車場にする人もいますが、
そんな考えも、あまり無かったころ、
近所の人や、農家さんなどと交流を深めていきました。
菜園の話などしつつ、いろいろな人とお話をしてくなかで、
知恵のあるおじいちゃんや、おばあちゃんに聞きながら
家の勉強をしていたはずなんです。
その土地の住宅事情を聞きつつ、家について勉強をしてから
やっと、家を建てるということが多かったんです。
情報もゆっくり集め、
お金もしっかり溜めてから建てるので、
失敗も少なかったはずです。
若いときに、無理をして建てると
思っていたように建てることができず、
建て直したり、数年でリフォームしたりすることになってしまう。
世間に煽られて、建ててしまっている人もいるかもしれません。
例えば、「便利」で「安い」という土地には、
やはり、何かしらの事情があることが多いものです。
以前、親戚が土地を買おうとして
「一緒に見て欲しい」と相談されたことがあります。
確かに便利な場所でしたが、100メートル先は運河で
裏は2メートルの絶壁でした。
地震があったら、液状化は間違いないような土地でした。
家のこと、土地のこと、もっと興味を持って
ゆっくり時間をかけて勉強して
家を建てて欲しいものです。
大切な家族が、毎日暮らすための「家」なのですから。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
タグ :匠がもの申す
2014年02月02日
匠がもの申す第20弾「*家は手入れして使うもの」
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
一周忌を無事に終える事ができ、皆さんのおかげです。
少しの間、家族も増えるので楽しくなりそうな棟梁です。
さて、一周忌も無時終わったんですが、すっかり写真も撮り忘れてしまい、
ただ、少し疲れが残った位でご報告をするだけになってしまいました。
そんな訳で、匠がもの申す第20弾です。
住まいは必ず手を入れなくてはなりません。
そんな思いをようで頂けるとありがたいです。

*家は手入れして使うもの
最近、「家を手入れする」という概念が
なんだか減ってきているような気がします。
モノも手入れすることがなくなり
使い捨て時代になってしまったからかもしれません。
家というものは、修理をしつつ長く持たせるものです。
構造さえしっかりしていれば、
あちこち壊れてきても、その部分だけを修理すれば
長持ちするはずなのです。
例えば、水回り。
壊れてきて、当たり前なのです。
昔の家は、どうなっていたかご存じでしょうか。
キッチンは土間だったんですよね。
お風呂、洗面所、トイレなどの
水回りを外に持っていくことで
家を守っていたんですね。
「便利」を優先するために、
水回りを家のなかに持ってきてしまったわけです。
便利にさせたひとつの要因は、
水道という文明の利器の発達も関係していますよね。
蛇口をひねれば、どこでも水が出る。
でも、水を流すということは、必ず排水がある。
そこに湿気が溜まるものなんです。
お風呂場の場合、普通の湯船とタイル張りの壁だと、
タイルの目地のところから湿気が外に出ているものです。
壁に亀裂が少し入っていたら、
湿気によって、割れてきているということです。
水が目地から壁のなかに入って、床に流れているんです。
そこに、シロアリが寄ってくるんですね。
湿気を溜めないようにするには、換気するしかありません。
一昔前に建てられた家は、床が少し低めなので、
湿気が多いと、基礎もしくは土間に溜まった湿気が上がってきて、
洗面所の床がプカプカと柔らかくなってくるんですね。
最近のユニットバスの場合は、二重パン構造になっていて、
床に水が落ちないようになっているので、
僕も、そういったユニットバスを使っています。
水回りについては、少しでも「おかしいかな?」と思った時点で
見に来てもらうことです。
被害が少なくて済みます。
でも、散々使った挙げ句の果てに修理すると、
洗面台もお風呂も変えないと……ということになります。
そうなると何百万円というリフォームになってしまうんですね。
虫歯と同じで、放っておくと、ひどくなるんですね。
2階にベランダを造ることがありますが、
あれも、実は、10年に一度は、塗り直しが必要なんです。
FRP工法という塗装をすることが多いんですが、
3~4層ほどのトップコートが剥がれて見えてきます。
そうなると、下地まで傷んでしまう。
本当は、5~10年の間に、一度、塗り直しをしたほうがいいんですね。
内ベランダの場合は、屋根があるので、まだ長持ちします。
でも、雨ざらしのベランダは、常に直射日光と雨風が当たり
風化も早いんです。
外壁サイディングなどもそうです。
ペンキ屋さんが吹き付けてくれるペンキ塗装は、10~15年しか持ちません。
塗り直しが必要になってくるのです。
家というものは壊れることが前提です。
メンテナンスは、必須です。
壊れない家はありません。
また、大事に使うお客さんと、そうではない人とでは
実の持ちが違うんですね。
家を持たせるためのポイントは、やっぱり「換気」。
僕が建てる場合は、とにかく自然の素材を使い、
土壁はもちろん、床も呼吸できるようにして、
大きな窓で、風や光を取り入れ、循環させています。
それと、「モノを置かない」こと。
昔の家が、今よりもきれいなのは、
モノが少なかったからだと思います。
モノが多いと、家を傷めてしまいます。
埃も多くなりますし、掃除も大変です。
埃が溜まれば、家にも住む人にも悪影響です。
僕が建てるときには、
できるだけ家具を外に置かないように、
大きなクローゼットにするようにしています。
クローゼットのなかに、ホームセンターなどにある
キャスター付きの衣装ケースを買ってきて
うまく使えばいいと、お勧めしています。
ベッドで寝る習慣が定着してきたことで
押し入れの必要がなくなり、クローゼットが好まれています。
お年寄りは引き戸が使い慣れている方が多いのですが、
折れ戸は手前に折れてくるので、その分、スペースが必要なので
部屋も実際にはその前にはモノを置けません。
実は、折れ戸のレールにも埃が溜まりやすいので
僕は、引き戸や襖が、お勧めです。
土間や段差があることによるメリットや、障子や襖の気密性など、
以前の記事『日本家屋はエコで健康』にも記していますので
参考に読んでみてくださいね。
みなさんにやっぱりもっと家のことについて
もっと勉強して欲しいと、つくづく思います。
なぜ、最近の人が家のことについて
詳しくなくなってしまったのか。
次回、お話ししたいと思います。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
一周忌を無事に終える事ができ、皆さんのおかげです。
少しの間、家族も増えるので楽しくなりそうな棟梁です。
さて、一周忌も無時終わったんですが、すっかり写真も撮り忘れてしまい、
ただ、少し疲れが残った位でご報告をするだけになってしまいました。
そんな訳で、匠がもの申す第20弾です。
住まいは必ず手を入れなくてはなりません。
そんな思いをようで頂けるとありがたいです。
*家は手入れして使うもの
最近、「家を手入れする」という概念が
なんだか減ってきているような気がします。
モノも手入れすることがなくなり
使い捨て時代になってしまったからかもしれません。
家というものは、修理をしつつ長く持たせるものです。
構造さえしっかりしていれば、
あちこち壊れてきても、その部分だけを修理すれば
長持ちするはずなのです。
例えば、水回り。
壊れてきて、当たり前なのです。
昔の家は、どうなっていたかご存じでしょうか。
キッチンは土間だったんですよね。
お風呂、洗面所、トイレなどの
水回りを外に持っていくことで
家を守っていたんですね。
「便利」を優先するために、
水回りを家のなかに持ってきてしまったわけです。
便利にさせたひとつの要因は、
水道という文明の利器の発達も関係していますよね。
蛇口をひねれば、どこでも水が出る。
でも、水を流すということは、必ず排水がある。
そこに湿気が溜まるものなんです。
お風呂場の場合、普通の湯船とタイル張りの壁だと、
タイルの目地のところから湿気が外に出ているものです。
壁に亀裂が少し入っていたら、
湿気によって、割れてきているということです。
水が目地から壁のなかに入って、床に流れているんです。
そこに、シロアリが寄ってくるんですね。
湿気を溜めないようにするには、換気するしかありません。
一昔前に建てられた家は、床が少し低めなので、
湿気が多いと、基礎もしくは土間に溜まった湿気が上がってきて、
洗面所の床がプカプカと柔らかくなってくるんですね。
最近のユニットバスの場合は、二重パン構造になっていて、
床に水が落ちないようになっているので、
僕も、そういったユニットバスを使っています。
水回りについては、少しでも「おかしいかな?」と思った時点で
見に来てもらうことです。
被害が少なくて済みます。
でも、散々使った挙げ句の果てに修理すると、
洗面台もお風呂も変えないと……ということになります。
そうなると何百万円というリフォームになってしまうんですね。
虫歯と同じで、放っておくと、ひどくなるんですね。
2階にベランダを造ることがありますが、
あれも、実は、10年に一度は、塗り直しが必要なんです。
FRP工法という塗装をすることが多いんですが、
3~4層ほどのトップコートが剥がれて見えてきます。
そうなると、下地まで傷んでしまう。
本当は、5~10年の間に、一度、塗り直しをしたほうがいいんですね。
内ベランダの場合は、屋根があるので、まだ長持ちします。
でも、雨ざらしのベランダは、常に直射日光と雨風が当たり
風化も早いんです。
外壁サイディングなどもそうです。
ペンキ屋さんが吹き付けてくれるペンキ塗装は、10~15年しか持ちません。
塗り直しが必要になってくるのです。
家というものは壊れることが前提です。
メンテナンスは、必須です。
壊れない家はありません。
また、大事に使うお客さんと、そうではない人とでは
実の持ちが違うんですね。
家を持たせるためのポイントは、やっぱり「換気」。
僕が建てる場合は、とにかく自然の素材を使い、
土壁はもちろん、床も呼吸できるようにして、
大きな窓で、風や光を取り入れ、循環させています。
それと、「モノを置かない」こと。
昔の家が、今よりもきれいなのは、
モノが少なかったからだと思います。
モノが多いと、家を傷めてしまいます。
埃も多くなりますし、掃除も大変です。
埃が溜まれば、家にも住む人にも悪影響です。
僕が建てるときには、
できるだけ家具を外に置かないように、
大きなクローゼットにするようにしています。
クローゼットのなかに、ホームセンターなどにある
キャスター付きの衣装ケースを買ってきて
うまく使えばいいと、お勧めしています。
ベッドで寝る習慣が定着してきたことで
押し入れの必要がなくなり、クローゼットが好まれています。
お年寄りは引き戸が使い慣れている方が多いのですが、
折れ戸は手前に折れてくるので、その分、スペースが必要なので
部屋も実際にはその前にはモノを置けません。
実は、折れ戸のレールにも埃が溜まりやすいので
僕は、引き戸や襖が、お勧めです。
土間や段差があることによるメリットや、障子や襖の気密性など、
以前の記事『日本家屋はエコで健康』にも記していますので
参考に読んでみてくださいね。
みなさんにやっぱりもっと家のことについて
もっと勉強して欲しいと、つくづく思います。
なぜ、最近の人が家のことについて
詳しくなくなってしまったのか。
次回、お話ししたいと思います。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年12月13日
第19弾 匠がもの申す!!
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
作業場で仕事をしていると、足先からキンキンに、
冷えて来て、冬が来た事を再認識した棟梁です。
さて、匠がもの申すも第19弾です。
木材を乾燥すると、いろんな事が起きて来ます。
乾燥させることの重要さ、木を見る目をここで養った棟梁です。
棟梁の思いなので、さまざまなご意見はあると思いますがご了承ください。
*木を寝かせるということ
~100坪のスペースに15年生までがずらり~
材木を「寝かせる」という言い方をします。
乾燥させるために置いておくことを意味します。
寝かせるのは、含水率をしっかり下げるため。

切ったばかりの木は、生きているわけですから
根っこから水を吸い上げているため水分を含んでいます。
根かせて乾いていくに従って、その子(木)の癖が出てくるのです。
材木屋さんで、材木を何年も寝かせている
ということは、なかなかありません。大工も同じです。
なぜなら、材木を寝かせておくには
それなりのスペースが必要だからです。
それでも、僕は安心して建てたいので
約100坪のスペースに、たくさんの材木をいつも寝かせています。
なかには15年の子もいます。
5年ほど寝かせると、通し柱として使えない子(木)も出てきます。
製材にかけると、一度はまっすぐになるのですが
含水率が落ちていくと、再び、ねじれてくるのです。
最初は6寸(約18cm)だったものが、
曲がってきたものを再度、製材にかけると5寸(約15cm)になるなど
どんどん細くなっていってしまうので、
そうなると、通し柱には使えません。
別の場所に使うことになります。
ねじれている子(木)は、支え合う所に持っていくしかなくなり
周りのみんながそれを、支えなければならないのです。
ねじれそうになるのを、我慢してもらうしかないんですね。
最初は、どの子もみんな普通に四角い材木なんです。
でも、寝かせておくと、すぐにねじれていくのがわかります。
一番ねじれがひどかった子(木)は、
7寸角(約21cm)の1寸(3cm)ほども、ねじれました。
製材をかけてみたぐらいでは、わからなかったのですが
ちょっと穴が空いていたので、半分に切ってみたら
もの凄く固いんですよ。固くて、固くて。
そして、中に腐りが入っていました。
どうやら、まだ若いうちに雷か何かが落ちたのでしょう。
太い枝が折れてしまったようだということがわかりました。
ねじれている子(木)は短い管柱ぐらいにしか使えないのですが、
その子は、管柱に使うのすら難しそうでした。
いじめられた子(木)は、ねじくれていっちゃうんですね。
うまくつかってあげたいけど、難しい。
しかも、そういう子(木)に限って、顔はいい。
イケメンなんですねぇ!(笑)
そんなわけで、見た目が白くてきれいな柱が
家の奥の隅っこのほうの短い柱に収まっているということも
実は、あるんですねぇ(笑)。
そうやって、どの子もゆっくり寝かせることで
適材適所に、どう収めてあげればいいのか
気長に見てあげています。
その子(木)たちのことを何年も見て把握します。
だからこそ、かなり曲がっている長い柱でも、
自信を持って組むことができるんですね。
「家を一件建てるには、山ごと買え」とは
法隆寺の鬼と呼ばれた、宮大工棟梁の西岡常一氏の言葉。
実際に、山ごと買えたなら、
南で育った子は、南で、
北で育った子は、北で使うなど
育った通りの配置にしてやることで、
それぞれの特長を活かせると言われています。
そんなことができれば……
そして、それを寝かせてから使えたら
さらに丈夫で安心できる家を建てられるでしょうね。
こんばんは。
作業場で仕事をしていると、足先からキンキンに、
冷えて来て、冬が来た事を再認識した棟梁です。
さて、匠がもの申すも第19弾です。
木材を乾燥すると、いろんな事が起きて来ます。
乾燥させることの重要さ、木を見る目をここで養った棟梁です。
棟梁の思いなので、さまざまなご意見はあると思いますがご了承ください。
*木を寝かせるということ
~100坪のスペースに15年生までがずらり~
材木を「寝かせる」という言い方をします。
乾燥させるために置いておくことを意味します。
寝かせるのは、含水率をしっかり下げるため。
切ったばかりの木は、生きているわけですから
根っこから水を吸い上げているため水分を含んでいます。
根かせて乾いていくに従って、その子(木)の癖が出てくるのです。
材木屋さんで、材木を何年も寝かせている
ということは、なかなかありません。大工も同じです。
なぜなら、材木を寝かせておくには
それなりのスペースが必要だからです。
それでも、僕は安心して建てたいので
約100坪のスペースに、たくさんの材木をいつも寝かせています。
なかには15年の子もいます。
5年ほど寝かせると、通し柱として使えない子(木)も出てきます。
製材にかけると、一度はまっすぐになるのですが
含水率が落ちていくと、再び、ねじれてくるのです。
最初は6寸(約18cm)だったものが、
曲がってきたものを再度、製材にかけると5寸(約15cm)になるなど
どんどん細くなっていってしまうので、
そうなると、通し柱には使えません。
別の場所に使うことになります。
ねじれている子(木)は、支え合う所に持っていくしかなくなり
周りのみんながそれを、支えなければならないのです。
ねじれそうになるのを、我慢してもらうしかないんですね。
最初は、どの子もみんな普通に四角い材木なんです。
でも、寝かせておくと、すぐにねじれていくのがわかります。
一番ねじれがひどかった子(木)は、
7寸角(約21cm)の1寸(3cm)ほども、ねじれました。
製材をかけてみたぐらいでは、わからなかったのですが
ちょっと穴が空いていたので、半分に切ってみたら
もの凄く固いんですよ。固くて、固くて。
そして、中に腐りが入っていました。
どうやら、まだ若いうちに雷か何かが落ちたのでしょう。
太い枝が折れてしまったようだということがわかりました。
ねじれている子(木)は短い管柱ぐらいにしか使えないのですが、
その子は、管柱に使うのすら難しそうでした。
いじめられた子(木)は、ねじくれていっちゃうんですね。
うまくつかってあげたいけど、難しい。
しかも、そういう子(木)に限って、顔はいい。
イケメンなんですねぇ!(笑)
そんなわけで、見た目が白くてきれいな柱が
家の奥の隅っこのほうの短い柱に収まっているということも
実は、あるんですねぇ(笑)。
そうやって、どの子もゆっくり寝かせることで
適材適所に、どう収めてあげればいいのか
気長に見てあげています。
その子(木)たちのことを何年も見て把握します。
だからこそ、かなり曲がっている長い柱でも、
自信を持って組むことができるんですね。
「家を一件建てるには、山ごと買え」とは
法隆寺の鬼と呼ばれた、宮大工棟梁の西岡常一氏の言葉。
実際に、山ごと買えたなら、
南で育った子は、南で、
北で育った子は、北で使うなど
育った通りの配置にしてやることで、
それぞれの特長を活かせると言われています。
そんなことができれば……
そして、それを寝かせてから使えたら
さらに丈夫で安心できる家を建てられるでしょうね。
タグ :匠がもの申す
2013年11月19日
匠がもの申す 第18弾 「大黒柱の値段」
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
なんだか、今日は風が強く、ぐっと寒くなり、
明日からは、ももひきを・・・と考え中の棟梁です。
さて今日は、「匠がもの申す」 第18弾です。
木には、いろんな種類があり、少しづつ違いがあるので、
値段も違って来ます。
そんな事を少し書きました。
~大黒柱の値段~
実は、僕のホームページは
「大黒柱」「値段」という検索で
来てくれている人がたくさんいらっしゃいます。

そこで、今回は思い切って
大黒柱の値段について、お話ししたいと思います。
大黒柱の値段を、ざっくりとお伝えしますと
約50~300万円の間ぐらいだと言えます。
なぜ、それほど幅があるのかというと、
材木の種類、大きさよって、まったく値段が異なるからです。
・産地
・年輪の幅
・赤身が多いか
・まっすぐかどうか
・ねじれていないかどうか
・枝がたくさんなかったかどうか
などの条件によって、材木の値段は
同じ種類であってもまったく違います。
*産地
長野県や三重県にしか無い檜は
目がつんでいて、人気です。
三重県の檜は、
お伊勢さんに使われる長野県の檜に。
香りが近いと言われています。
「目がつんでる」と僕らが言うのは
年輪の幅が狭いという意味です。
*年輪の幅
目がつんでる(年輪の幅が狭い)ものは、
木目が美しくて表情が違います。
それに、油が強くて根性も強い……つまり長持ちするのです。
*赤身が多いか
材木の赤い部分を「赤身(あかみ)」、
白っぽくて明るい部分を「白太(しらた)」と言います。
材木の中心部が赤身で、
外側が白太になっています。
中心の赤身の部分は、細胞がすでに活動を終えており
水もほとんど含まれておらず、丈夫なのです。
*まっすぐかどうか
*ねじれていないかどうか
もちろん、まっすぐに育った
ねじれの少ない子が、重宝されます。
木は育ってきた環境の影響を強く受けています。
例えば、丘陵地で傾斜のある場所に育った子(木)は
まず横や斜め向きに顔を出した後、曲がって太陽に向かって伸びていきます。
つまり根っこ近くで、90度近く曲がってから上に伸びることになります。
また、風が強く吹く場所で育った子は
いつも同じ方向からの風に吹かれています。
こういう子たちは、ねじれているのです。
ねじれた子を、そうとは知らずに通し柱などに使うと
「家を持っていかれる」という言い方をします。
ねじれる柱が、家全体を歪ませてしまうのです。
*枝がたくさんなかったかどうか
枝がたくさんあったということは、
それだけ節が多いということになります。
節が少ないほどきれいで、高額になります。
こういった材木の特長と、種類。
そして、見た目の美しさから、大黒柱の値段は決まります。
価格は材木屋さんが決めています。
自分で見てその値段で納得がいくかどうか
……ということになりますが、
素人目には、なかなか価値や値段はわかりにくいでしょう。
「その材木屋さんで買う」と決めたうえでなら
実際に材木を見せてもらえると思いますが、
買う気が無いなら、それも難しいと思います。
もちろん、僕のところで家を建てる場合なら
寝かせているたくさんの材木をお見せして
値段もお教えすることはできますよ。
参考までに、この大黒柱は

約150年生の欅で、約100万円ぐらいのものです。
36cm角で、白太がほとんどないものです。
欅はクセが強いと言われていますが、
この子(木)は、僕のところで何年も寝かせていたので、
まっすぐな子だということも保証できますので、安心ですよね。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
なんだか、今日は風が強く、ぐっと寒くなり、
明日からは、ももひきを・・・と考え中の棟梁です。
さて今日は、「匠がもの申す」 第18弾です。
木には、いろんな種類があり、少しづつ違いがあるので、
値段も違って来ます。
そんな事を少し書きました。
~大黒柱の値段~
実は、僕のホームページは
「大黒柱」「値段」という検索で
来てくれている人がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は思い切って
大黒柱の値段について、お話ししたいと思います。
大黒柱の値段を、ざっくりとお伝えしますと
約50~300万円の間ぐらいだと言えます。
なぜ、それほど幅があるのかというと、
材木の種類、大きさよって、まったく値段が異なるからです。
・産地
・年輪の幅
・赤身が多いか
・まっすぐかどうか
・ねじれていないかどうか
・枝がたくさんなかったかどうか
などの条件によって、材木の値段は
同じ種類であってもまったく違います。
*産地
長野県や三重県にしか無い檜は
目がつんでいて、人気です。
三重県の檜は、
お伊勢さんに使われる長野県の檜に。
香りが近いと言われています。
「目がつんでる」と僕らが言うのは
年輪の幅が狭いという意味です。
*年輪の幅
目がつんでる(年輪の幅が狭い)ものは、
木目が美しくて表情が違います。
それに、油が強くて根性も強い……つまり長持ちするのです。
*赤身が多いか
材木の赤い部分を「赤身(あかみ)」、
白っぽくて明るい部分を「白太(しらた)」と言います。
材木の中心部が赤身で、
外側が白太になっています。
中心の赤身の部分は、細胞がすでに活動を終えており
水もほとんど含まれておらず、丈夫なのです。
*まっすぐかどうか
*ねじれていないかどうか
もちろん、まっすぐに育った
ねじれの少ない子が、重宝されます。
木は育ってきた環境の影響を強く受けています。
例えば、丘陵地で傾斜のある場所に育った子(木)は
まず横や斜め向きに顔を出した後、曲がって太陽に向かって伸びていきます。
つまり根っこ近くで、90度近く曲がってから上に伸びることになります。
また、風が強く吹く場所で育った子は
いつも同じ方向からの風に吹かれています。
こういう子たちは、ねじれているのです。
ねじれた子を、そうとは知らずに通し柱などに使うと
「家を持っていかれる」という言い方をします。
ねじれる柱が、家全体を歪ませてしまうのです。
*枝がたくさんなかったかどうか
枝がたくさんあったということは、
それだけ節が多いということになります。
節が少ないほどきれいで、高額になります。
こういった材木の特長と、種類。
そして、見た目の美しさから、大黒柱の値段は決まります。
価格は材木屋さんが決めています。
自分で見てその値段で納得がいくかどうか
……ということになりますが、
素人目には、なかなか価値や値段はわかりにくいでしょう。
「その材木屋さんで買う」と決めたうえでなら
実際に材木を見せてもらえると思いますが、
買う気が無いなら、それも難しいと思います。
もちろん、僕のところで家を建てる場合なら
寝かせているたくさんの材木をお見せして
値段もお教えすることはできますよ。
参考までに、この大黒柱は
約150年生の欅で、約100万円ぐらいのものです。
36cm角で、白太がほとんどないものです。
欅はクセが強いと言われていますが、
この子(木)は、僕のところで何年も寝かせていたので、
まっすぐな子だということも保証できますので、安心ですよね。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年10月13日
匠が物申す 第17弾 ■餅投げの風習 ~家族の絆、地域の絆~
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
匠がもの申す第17弾
■餅投げの風習 ~家族の絆、地域の絆~
建前の上棟式。
みなさんの地域では、どんなことをしますか?
赤飯を配るという地域もあるそうですね。
僕のいる東三河方面では、
「餅投げ」の風習があります。
二階から餅を投げるんですが、
昔は、その場でお餅をついて投げたそうです。
全国的に、同じような風習があるようですね。
今回、7月に上棟式をしたお客様の場合、
施主のHさんご本人、そのお兄さんとお父さん、
僕の4人で、一俵分ぐらいのお餅を投げました。

まず最初に、四角に向かってお餅を投げますが
この四角のお餅を手に入れた人は
次に家を建てることができると言われています。
結婚式のブーケみたいな感じですね。
その後、軒先のほうに向かって投げます。
現在は、お餅のほかに、お菓子、お金、手ぬぐいやタオル
といったものを、袋に入れて投げます。
お金の金額は、例えば、7,778円分、8,888円分など
縁起のいい合計金額のお金を、小銭で用意して、
半紙のおひねりにして投げます。
家族みんなで相談して、用意をして、
そして、当日は男性陣が投げるのです。

昔は、家を建てるということは、
元服、結婚、出産、お葬式などと並ぶ
家族の大きな行事だったんです。
「餅投げ」は、「幸せのお裾分け」なんですね。
このあたりでは、餅投げをする日に
目印として「竹の笹」を立てておきます。
すると、通りがかった子どもたちから
「餅投げ、何時からですか?」などと声がかかります。
誰でも参加できますので、近所の子どもたちや
見知らぬ人たちもたくさん集まってきます。
今回もおそらく100~150人ぐらい集まって来られたでしょうか。
みなさん、お餅やお菓子を楽しそうに持ち帰られました。
家を建てるということは、自分の城を持つということ。
その幸せを、ご近所さんと分け合えるって、素敵ですよね。
血のつながりもない、顔見知りでもない、
いろいろな人と、幸せを共有できるんですから。
昔の人はこうやって、家のなかも村のなかも
風通しのいい人間関係を築いていたんでしょうね。
Hさんご一家も、新築後、きっと
ご近所さんと仲よく暮らしていけることと思います。
楽しみですね!
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
匠がもの申す第17弾
■餅投げの風習 ~家族の絆、地域の絆~
建前の上棟式。
みなさんの地域では、どんなことをしますか?
赤飯を配るという地域もあるそうですね。
僕のいる東三河方面では、
「餅投げ」の風習があります。
二階から餅を投げるんですが、
昔は、その場でお餅をついて投げたそうです。
全国的に、同じような風習があるようですね。
今回、7月に上棟式をしたお客様の場合、
施主のHさんご本人、そのお兄さんとお父さん、
僕の4人で、一俵分ぐらいのお餅を投げました。
まず最初に、四角に向かってお餅を投げますが
この四角のお餅を手に入れた人は
次に家を建てることができると言われています。
結婚式のブーケみたいな感じですね。
その後、軒先のほうに向かって投げます。
現在は、お餅のほかに、お菓子、お金、手ぬぐいやタオル
といったものを、袋に入れて投げます。
お金の金額は、例えば、7,778円分、8,888円分など
縁起のいい合計金額のお金を、小銭で用意して、
半紙のおひねりにして投げます。
家族みんなで相談して、用意をして、
そして、当日は男性陣が投げるのです。
昔は、家を建てるということは、
元服、結婚、出産、お葬式などと並ぶ
家族の大きな行事だったんです。
「餅投げ」は、「幸せのお裾分け」なんですね。
このあたりでは、餅投げをする日に
目印として「竹の笹」を立てておきます。
すると、通りがかった子どもたちから
「餅投げ、何時からですか?」などと声がかかります。
誰でも参加できますので、近所の子どもたちや
見知らぬ人たちもたくさん集まってきます。
今回もおそらく100~150人ぐらい集まって来られたでしょうか。
みなさん、お餅やお菓子を楽しそうに持ち帰られました。
家を建てるということは、自分の城を持つということ。
その幸せを、ご近所さんと分け合えるって、素敵ですよね。
血のつながりもない、顔見知りでもない、
いろいろな人と、幸せを共有できるんですから。
昔の人はこうやって、家のなかも村のなかも
風通しのいい人間関係を築いていたんでしょうね。
Hさんご一家も、新築後、きっと
ご近所さんと仲よく暮らしていけることと思います。
楽しみですね!
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年09月16日
匠が物申す 第16弾 屋根土と壁土 ~土は育つ、土は蘇る~
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
皆さん、18号台風の被害は無かったでしょうか?
棟梁のお客さん4件の方から被害のお電話があり、
1軒を明日にさせて頂き、
対応させて頂きました。
被害に会われた方々お見舞い申し上げます。
そんな中、棟梁は、現場に出向いたんですが、
すっかり、写真を撮り忘れて大失態です(笑)
と言う事で、匠が物申す第16弾をアップする事にしました。
あくまでも、棟梁の意見でありますので、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
■屋根土と壁土 ~土は育つ、土は蘇る~
屋根の瓦は、現在の工法では、
野地板の上に、防水材を張り、その上に、
桟(さん)を打ち、その桟に瓦を留めて葺(ふ)いていくようです。
僕の場合は、防水材も張りますが、その上に
檜皮(ひがわ=ヒノキの皮)を敷いていきます。

その檜皮の上に桟を打ってから屋根土を乗せてから
瓦を葺いていくのです。
阪神淡路大震災の後から、
「屋根土を乗せると倒れやすい」と、よく言われました。
でも、僕のような従来工法で建てた家なら、
屋根の重さが原因で倒れるということはまずありません。
柱の重みも、屋根土の重さも、
むしろ、倒壊を防ぐためには必要なんです。
それに、屋根土は断熱効果もあります。
メンテナンスさえきちんとしていれば
孫末代まで長持ちする、丈夫な家。
それが、従来工法の建て方です。
さて、この屋根土や、土壁の土を作っているのが、
通称、ドロコン屋さんです。

赤土+砂(砕石)+粘土+藁すさ+水
で、できています。
水や藁すさの配合や、寝かせる期間によって
屋根土になったり、壁土になったりします。

赤土は、その土地のものを使います。
赤土のままだと干割れ(ひわれ)しやすいのですが、
この状態を「土が『若い』」なんて言います。
崩れやすいのです。
そこに、水や藁すさを足しながら、
何ヶ月も寝かせて、土を育てていくのですが、
一週間もしないうちに、発酵して藁が柔らかくなるんです。
壁土は、屋根土より水分も藁も多めで柔らかく
屋根土のほうが、固いんですね。
もし屋根土が柔らか過ぎると、瓦が沈んでしまいます。
固い土にぐっと抑えながら、密着させていくのです。
屋根土は、長く置き過ぎてはいけません。
逆に、壁土は長く置かなければ、
粘りが出ないので期間を要します。
「お城の支度は材木よりも先に土を用意しろ」
と言われていたほどです。
壁土は、藁が発酵していくので、かなり匂いもあります。
でも、それは塗り終わって乾いてくると
驚くほど消えてしまうんですね。

育てている土をひっくり返すと、中は真っ黒です。
微生物が、藁をくいながら発酵していくんです。
ひっくり返して新しい空気を入れたり
干ばつが続くと水を与えたり
水や空気を与えながら、時間をかけて育てていくんですね。
水を加えている限り、土は発酵し続けますが、
乾き出すと微生物も活動できずに固まっていきます。
そうして、使われた土たちは、リサイクルできるって
ご存じでしたか?
何百年も経ってから、解体して出てきた土も
漆喰さえ取ってしまえば、
水を与えてやると復活できる。
再利用できるので、永久に使えるんですね。
昔の人はぐるぐる循環するように、考えていたんです。
古くなった城や古民家を解体しても、
柱も土も使えるんですね。
僕は、いつかボルトも一切使わない、
循環できる素材だけで家を造りたいと思っています。
実際に、それをやっておられる大工さんが日本にいます。
僕も、それを目指しています。
日本の家と山林の関係も「循環」です。
興味のある方は『日本の仕事、日本の山』も
合わせてご覧くださいね。
※藁すさ:古い藁やむしろを2cmほどに切ったものを、叩いて水につけて柔らかくしたもの。
関東方面では、すさではなく「つた」といわれる。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
皆さん、18号台風の被害は無かったでしょうか?
棟梁のお客さん4件の方から被害のお電話があり、
1軒を明日にさせて頂き、
対応させて頂きました。
被害に会われた方々お見舞い申し上げます。
そんな中、棟梁は、現場に出向いたんですが、
すっかり、写真を撮り忘れて大失態です(笑)
と言う事で、匠が物申す第16弾をアップする事にしました。
あくまでも、棟梁の意見でありますので、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
■屋根土と壁土 ~土は育つ、土は蘇る~
屋根の瓦は、現在の工法では、
野地板の上に、防水材を張り、その上に、
桟(さん)を打ち、その桟に瓦を留めて葺(ふ)いていくようです。
僕の場合は、防水材も張りますが、その上に
檜皮(ひがわ=ヒノキの皮)を敷いていきます。
その檜皮の上に桟を打ってから屋根土を乗せてから
瓦を葺いていくのです。
阪神淡路大震災の後から、
「屋根土を乗せると倒れやすい」と、よく言われました。
でも、僕のような従来工法で建てた家なら、
屋根の重さが原因で倒れるということはまずありません。
柱の重みも、屋根土の重さも、
むしろ、倒壊を防ぐためには必要なんです。
それに、屋根土は断熱効果もあります。
メンテナンスさえきちんとしていれば
孫末代まで長持ちする、丈夫な家。
それが、従来工法の建て方です。
さて、この屋根土や、土壁の土を作っているのが、
通称、ドロコン屋さんです。
赤土+砂(砕石)+粘土+藁すさ+水
で、できています。
水や藁すさの配合や、寝かせる期間によって
屋根土になったり、壁土になったりします。
赤土は、その土地のものを使います。
赤土のままだと干割れ(ひわれ)しやすいのですが、
この状態を「土が『若い』」なんて言います。
崩れやすいのです。
そこに、水や藁すさを足しながら、
何ヶ月も寝かせて、土を育てていくのですが、
一週間もしないうちに、発酵して藁が柔らかくなるんです。
壁土は、屋根土より水分も藁も多めで柔らかく
屋根土のほうが、固いんですね。
もし屋根土が柔らか過ぎると、瓦が沈んでしまいます。
固い土にぐっと抑えながら、密着させていくのです。
屋根土は、長く置き過ぎてはいけません。
逆に、壁土は長く置かなければ、
粘りが出ないので期間を要します。
「お城の支度は材木よりも先に土を用意しろ」
と言われていたほどです。
壁土は、藁が発酵していくので、かなり匂いもあります。
でも、それは塗り終わって乾いてくると
驚くほど消えてしまうんですね。
育てている土をひっくり返すと、中は真っ黒です。
微生物が、藁をくいながら発酵していくんです。
ひっくり返して新しい空気を入れたり
干ばつが続くと水を与えたり
水や空気を与えながら、時間をかけて育てていくんですね。
水を加えている限り、土は発酵し続けますが、
乾き出すと微生物も活動できずに固まっていきます。
そうして、使われた土たちは、リサイクルできるって
ご存じでしたか?
何百年も経ってから、解体して出てきた土も
漆喰さえ取ってしまえば、
水を与えてやると復活できる。
再利用できるので、永久に使えるんですね。
昔の人はぐるぐる循環するように、考えていたんです。
古くなった城や古民家を解体しても、
柱も土も使えるんですね。
僕は、いつかボルトも一切使わない、
循環できる素材だけで家を造りたいと思っています。
実際に、それをやっておられる大工さんが日本にいます。
僕も、それを目指しています。
日本の家と山林の関係も「循環」です。
興味のある方は『日本の仕事、日本の山』も
合わせてご覧くださいね。
※藁すさ:古い藁やむしろを2cmほどに切ったものを、叩いて水につけて柔らかくしたもの。
関東方面では、すさではなく「つた」といわれる。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年08月18日
第15回を迎えた匠がもの申す
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
今日は、午前中はお客さんと、
タカラスタンダードに行き商品説明、
午後からは、ゆっくりできたそんな一日を過ごした棟梁です。
さて、匠ががもの申すも15回を迎えました。
棟梁の、思い少し強く出してみました。

*家のこと勉強していますか*
家を建てる。
家を買う。
今は、家を買う時代のようです。
文字通り、家を「買う」のです。
テレビで聞いたなぁというメーカーさんに頼んだり
住宅展示場に行って、サンプルを見たり
すでに建ててある家を観にいって買うのです。
家を「建てる」という感覚が
日本の文化から無くなりつつあります。
前回、お話ししたように、
基礎工事の方法は、どんどん変わっています。
建てる土地の地盤によりますが、
地面全体を覆うようにビニールシートを敷き
その上にコンクリートを全面に流し込む
ベタ基礎が主流になりつつあります。
ところが、そうではない、石場建て(礎石建て)で
家を建てる工務店さんもあります。
礎石の上に柱を置いて建てる従来工法で
昔ながらの社寺建築と同じ方法です。
石の上に柱が乗っているだけということに
驚かれる方も多いのですが
柱や屋根が重い分、加重がしっかりかかるので
倒れたりずれたりすることはありません。
今の建築基準法の下で、
この、直接、礎石の上に柱を立てる
「石場建て」で建築するのは困難になっています。
まず、建築申請しても許可が下りにくいのです。
聞くところによると、
許可が下りるのに、なんと1年もかかるそうです。
通常は約1週間もあれば許可が下りるのに、ですよ。
確認申請を通すには、技術が必要なんです。
礎石の加重計算など設計士さんにも知識がいるのです。
とはいっても、
「どうしても昔ながらの工法で建てたい!」
という施主さんがいらっしゃる限り、
がんばって建てようとする大工さんも設計士さんも
必ず残っていくでしょう。
こういう流れを見ていると、僕はつくづく、
「建てる人」も、もっと勉強して欲しいと思います。
もっと「家」や「建築」について
知って欲しいのです。
例えば、僕のような大工が建てる和風建築も、
知らなければ、「選択肢」のなかに入りません。
なんとなくテレビで見て聞いたことのある
大手メーカーさんの名前がなじんでいたり、
住宅展示場を見回って、そこで決めてしまう
ということもあるでしょう。
知っている範囲で、
人は選ぶものですから。
でも、考えてみてください。
家は、ご自身が毎日暮らす場所です。
どういう工法で建てられると
どのようなメリット・デメリットがあるのか。
健康にいいのは、どういう家なのか。
よく勉強しないまま、「買う」のと、
何かどう違うのかを勉強して「建てる」のとでは
きっと、手に入れる「家」は違うはずです。
そして、その後の人生が、
まったく違ってくると思いませんか?
昔は、家を建てるのに、何年も何年も勉強しました。
それこそ、柱を一年に一本ずつ集めるような方もいました。
今のような住宅ローンなどもなく
コツコツとお金を貯めてから買うのが一般的だったので
みなさん、時間をかけて家の知識を得ることができたのです。
今は、若いうちに家を建てる人が増えて
勉強する時間があまりないまま
家を買ってしまうので、勉強する時間が無いのかもしれません。
それでも、数年だとしても、本当に納得の家を建てるなら
こういった基礎工事のこと、建築方法のこと、素材のこと
いろいろ学んでみることを、お勧めします。
きっと、本当に心地のいい家が建てられますよ。
この記事をお読み頂き、さまざまなご意見があるかと思いますが、
私、棟梁の思いを綴ったものでありますので、ご批判はあるかと思いますが、
その点につきましては、ご了承いただきますようにお願いいたします。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
今日は、午前中はお客さんと、
タカラスタンダードに行き商品説明、
午後からは、ゆっくりできたそんな一日を過ごした棟梁です。
さて、匠ががもの申すも15回を迎えました。
棟梁の、思い少し強く出してみました。
*家のこと勉強していますか*
家を建てる。
家を買う。
今は、家を買う時代のようです。
文字通り、家を「買う」のです。
テレビで聞いたなぁというメーカーさんに頼んだり
住宅展示場に行って、サンプルを見たり
すでに建ててある家を観にいって買うのです。
家を「建てる」という感覚が
日本の文化から無くなりつつあります。
前回、お話ししたように、
基礎工事の方法は、どんどん変わっています。
建てる土地の地盤によりますが、
地面全体を覆うようにビニールシートを敷き
その上にコンクリートを全面に流し込む
ベタ基礎が主流になりつつあります。
ところが、そうではない、石場建て(礎石建て)で
家を建てる工務店さんもあります。
礎石の上に柱を置いて建てる従来工法で
昔ながらの社寺建築と同じ方法です。
石の上に柱が乗っているだけということに
驚かれる方も多いのですが
柱や屋根が重い分、加重がしっかりかかるので
倒れたりずれたりすることはありません。
今の建築基準法の下で、
この、直接、礎石の上に柱を立てる
「石場建て」で建築するのは困難になっています。
まず、建築申請しても許可が下りにくいのです。
聞くところによると、
許可が下りるのに、なんと1年もかかるそうです。
通常は約1週間もあれば許可が下りるのに、ですよ。
確認申請を通すには、技術が必要なんです。
礎石の加重計算など設計士さんにも知識がいるのです。
とはいっても、
「どうしても昔ながらの工法で建てたい!」
という施主さんがいらっしゃる限り、
がんばって建てようとする大工さんも設計士さんも
必ず残っていくでしょう。
こういう流れを見ていると、僕はつくづく、
「建てる人」も、もっと勉強して欲しいと思います。
もっと「家」や「建築」について
知って欲しいのです。
例えば、僕のような大工が建てる和風建築も、
知らなければ、「選択肢」のなかに入りません。
なんとなくテレビで見て聞いたことのある
大手メーカーさんの名前がなじんでいたり、
住宅展示場を見回って、そこで決めてしまう
ということもあるでしょう。
知っている範囲で、
人は選ぶものですから。
でも、考えてみてください。
家は、ご自身が毎日暮らす場所です。
どういう工法で建てられると
どのようなメリット・デメリットがあるのか。
健康にいいのは、どういう家なのか。
よく勉強しないまま、「買う」のと、
何かどう違うのかを勉強して「建てる」のとでは
きっと、手に入れる「家」は違うはずです。
そして、その後の人生が、
まったく違ってくると思いませんか?
昔は、家を建てるのに、何年も何年も勉強しました。
それこそ、柱を一年に一本ずつ集めるような方もいました。
今のような住宅ローンなどもなく
コツコツとお金を貯めてから買うのが一般的だったので
みなさん、時間をかけて家の知識を得ることができたのです。
今は、若いうちに家を建てる人が増えて
勉強する時間があまりないまま
家を買ってしまうので、勉強する時間が無いのかもしれません。
それでも、数年だとしても、本当に納得の家を建てるなら
こういった基礎工事のこと、建築方法のこと、素材のこと
いろいろ学んでみることを、お勧めします。
きっと、本当に心地のいい家が建てられますよ。
この記事をお読み頂き、さまざまなご意見があるかと思いますが、
私、棟梁の思いを綴ったものでありますので、ご批判はあるかと思いますが、
その点につきましては、ご了承いただきますようにお願いいたします。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年07月17日
匠がもの申す 第14回 「呼吸する床」
*呼吸する床*
高機密、高断熱の住宅が、世間では求められています。
「寒さ」と「湿気」を避けるためです。
以前にも話しましたが、昔は、田んぼの田の字といって
ふすまで区切られた、たくさんの和室があり
ふすまを取り払うと、部屋がひとつになるように
建てられていました。
ふすまを開け放すと、すべての部屋に
風が通り抜けるようになっていたのですね。
そして、畳を上げると、
その下には土が見えていました。
床下の換気も良かったのです。
ところが、今の建築基準法では、
地盤調査の結果によっては、
基礎工事の段階で、土をすべて覆い隠すように、
コンクリートを流し込むことになっています。
一般に「べた基礎」と言われる基礎のやり方です。
阪神大震災以降に、増えてきました。
それ以前は、「布基礎(ぬのきそ)」といって、
壁、柱、部屋の仕切りなどの下のみ
コンクリートを打ってあり、
それ以外は地面が見えている状態でした。
地盤によっては、今も、布基礎でも構わないのですが
それでもなおかつ、後から土間の部分に
「防湿コンクリート」を流し込んで
蓋をするという処理をすることが増えています。
とにかく、土から湿気を上げないということに
とてもこだわるのです。
僕のような昔気質の大工の感覚では
このような土全体をコンクリートで塞ぐ
ということには、ちょっと抵抗があります。
せっかく、風通しのいい家を造り、
土壁で呼吸する壁を造っても、
呼吸できない床にしてしまうのが
何とも違和感があるのです。
そこで、僕が建てるときには、
このように、床に小さな穴をあけます。

工事中の雨水を排水するための穴は
施工後にすべて塞いでしまいますが
これとは、また別のものです。
僕の大工としての感覚では、
やはり、床も呼吸しているのが普通なんですね。
床が呼吸して初めて、空気が循環するはずなんです。
これぐらいの大きさの穴であれば
湿度には影響しません。
また、建築士さんのチェックが入りますので
そのときにOKをいただいています。
こうやって、少しでも、僕らの職人感覚を活かした
小さな技が、大工の建てる家には隠されています。
呼吸する壁。
呼吸する床。
生きている材木。
住まわれている方から
「森のなかにいるような透明感がある」
と言ってもらえるのは、風通しが良くて
家全体が呼吸しているからなんですね。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
高機密、高断熱の住宅が、世間では求められています。
「寒さ」と「湿気」を避けるためです。
以前にも話しましたが、昔は、田んぼの田の字といって
ふすまで区切られた、たくさんの和室があり
ふすまを取り払うと、部屋がひとつになるように
建てられていました。
ふすまを開け放すと、すべての部屋に
風が通り抜けるようになっていたのですね。
そして、畳を上げると、
その下には土が見えていました。
床下の換気も良かったのです。
ところが、今の建築基準法では、
地盤調査の結果によっては、
基礎工事の段階で、土をすべて覆い隠すように、
コンクリートを流し込むことになっています。
一般に「べた基礎」と言われる基礎のやり方です。
阪神大震災以降に、増えてきました。
それ以前は、「布基礎(ぬのきそ)」といって、
壁、柱、部屋の仕切りなどの下のみ
コンクリートを打ってあり、
それ以外は地面が見えている状態でした。
地盤によっては、今も、布基礎でも構わないのですが
それでもなおかつ、後から土間の部分に
「防湿コンクリート」を流し込んで
蓋をするという処理をすることが増えています。
とにかく、土から湿気を上げないということに
とてもこだわるのです。
僕のような昔気質の大工の感覚では
このような土全体をコンクリートで塞ぐ
ということには、ちょっと抵抗があります。
せっかく、風通しのいい家を造り、
土壁で呼吸する壁を造っても、
呼吸できない床にしてしまうのが
何とも違和感があるのです。
そこで、僕が建てるときには、
このように、床に小さな穴をあけます。

工事中の雨水を排水するための穴は
施工後にすべて塞いでしまいますが
これとは、また別のものです。
僕の大工としての感覚では、
やはり、床も呼吸しているのが普通なんですね。
床が呼吸して初めて、空気が循環するはずなんです。
これぐらいの大きさの穴であれば
湿度には影響しません。
また、建築士さんのチェックが入りますので
そのときにOKをいただいています。
こうやって、少しでも、僕らの職人感覚を活かした
小さな技が、大工の建てる家には隠されています。
呼吸する壁。
呼吸する床。
生きている材木。
住まわれている方から
「森のなかにいるような透明感がある」
と言ってもらえるのは、風通しが良くて
家全体が呼吸しているからなんですね。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年05月19日
大工棟梁のこだわり!
見に来て下さりありがとうございます。
こんばんは。
今日は、親父の100かにち、早いもんですね、
色々な事を学ばせて頂いています。
ありがとい事です。
さて今日は、「匠がもの申す」シリーズ第13弾です。
棟梁のこだわりを少し綴って見ました。
今、手がけさせているお客さんのお宅もこだわります!!
【いっぽんもん】
「いっぽんもん」という言葉があります。
継ぎ目のない、一本の材料のことです。
僕ら東三河の大工は、
この「いっぽんもん」と言われる
6m以上もの長い材料を使います。

ゆっくりしっかり乾かした材木は
それだけ長くても割れや歪みが少ないのです。
うちで寝てる子(乾かしている材木)なら
それが、確実に保証できる。
だから、うちでしっかり寝かせているんですね。
地域によっては4mより長い材木は使わないと聞きます。
加藤建築のある東三河は、山の多い土地で
地松が豊富で、そこら中にいっぱいあったので
昔は、長い木を使っていたんですね。
いっぽんもんの木は折れにくい。
繋いでしまうと、どうしても歪みに負担がかかります。
その歪みをなるべく大きくしないようにと
継ぎ手を細工する技術が発展してきたわけなのですが
いっぽんものだと、継ぎ手を作る必要さえなくて、
一番丈夫なわけです。
「三河の空っ風は、違うでな。
いっぽんでやると丈夫くなるでよ」
と、三河では、いっぽんもんにこだわってきました。
太平洋と伊勢湾に囲まれた渥美半島を含む
この三河の土地には、年中、強い風が吹いているんですね。
地震や台風の歴史にも関係あります。
例えば、雪の深い石川県では、
太平洋側の家に比べて、軒が深くなっている。
土地によって家の特徴も建て方も違うんですねぇ。
常に土地の気候や、歴史と、建築は関係しています。
川縁には材木問屋があるし、
大きなお城のあるところには、建築に関わる職人が多い。
このあたりの話も調べ出すとキリがないのですが
自分の土地について勉強すると面白いと思いますよ。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
こんばんは。
今日は、親父の100かにち、早いもんですね、
色々な事を学ばせて頂いています。
ありがとい事です。
さて今日は、「匠がもの申す」シリーズ第13弾です。
棟梁のこだわりを少し綴って見ました。
今、手がけさせているお客さんのお宅もこだわります!!
【いっぽんもん】
「いっぽんもん」という言葉があります。
継ぎ目のない、一本の材料のことです。
僕ら東三河の大工は、
この「いっぽんもん」と言われる
6m以上もの長い材料を使います。
ゆっくりしっかり乾かした材木は
それだけ長くても割れや歪みが少ないのです。
うちで寝てる子(乾かしている材木)なら
それが、確実に保証できる。
だから、うちでしっかり寝かせているんですね。
地域によっては4mより長い材木は使わないと聞きます。
加藤建築のある東三河は、山の多い土地で
地松が豊富で、そこら中にいっぱいあったので
昔は、長い木を使っていたんですね。
いっぽんもんの木は折れにくい。
繋いでしまうと、どうしても歪みに負担がかかります。
その歪みをなるべく大きくしないようにと
継ぎ手を細工する技術が発展してきたわけなのですが
いっぽんものだと、継ぎ手を作る必要さえなくて、
一番丈夫なわけです。
「三河の空っ風は、違うでな。
いっぽんでやると丈夫くなるでよ」
と、三河では、いっぽんもんにこだわってきました。
太平洋と伊勢湾に囲まれた渥美半島を含む
この三河の土地には、年中、強い風が吹いているんですね。
地震や台風の歴史にも関係あります。
例えば、雪の深い石川県では、
太平洋側の家に比べて、軒が深くなっている。
土地によって家の特徴も建て方も違うんですねぇ。
常に土地の気候や、歴史と、建築は関係しています。
川縁には材木問屋があるし、
大きなお城のあるところには、建築に関わる職人が多い。
このあたりの話も調べ出すとキリがないのですが
自分の土地について勉強すると面白いと思いますよ。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年04月25日
【棟梁の技量】 ~1つだけ失敗するという器~
【棟梁の技量】 ~1つだけ失敗するという器~
「建前」のときに
失敗が見つかることがあります。
それについて、僕らは
「間違いじゃないでね」と説明します。
というのも、
「完璧な家を建ててしまうと
その家主の家系は、それ以上繁盛しない」
と古くから言われているからなんですね。
間違いではなく、
施主さんを想ってのことだと説明するのです。
実際に、昔は、子どもや孫、ひ孫の代まで
ひとつの家に住んだので、
建物がその家系に大きく影響すると考えられていたのでしょう。
人から聞いた話なので、曖昧ですが
日光東照宮での話として聞いたものです。
この「1つだけ間違えると繁盛する」という
言い伝えから、棟梁は日光東照宮の繁盛
……つまり、徳川家の繁盛を願って
柱を一本だけ逆さまにして建てたそうです。
ただし、間違えていることがわかると大問題ですので
わからないように、その柱には彫刻を施したそうです。
ところがお披露目のときに、名も無いおばあさんに
「なんで、この柱だけ上下を間違えたまま建てたのか」
と指摘されてしまいました。
それを聞いた棟梁は責任を負って切腹した
という言い伝えがあります。
職人が素人に間違いを指摘されたわけですから
戦国時代なら、確かに切腹もあり得るかもしれません。
棟梁は、それぐらいに間違いにはシビアであり
将軍の「繁盛」は、今では想像できないぐらいの
とても重要なものだったのでしょうね。
僕の建てる家で見つかる間違いは、
もちろん小さなものです。
『つか』といって屋根の重さを分散して伝えるための
45cmぐらいの小さな柱があるのですが、
その長さを1cm5mm間違うなどの小さな失敗です。
僕らも、三度は確認するんですが
何千もの部材を使うわけですから
どうしても見落としが出てしまい、
それが建前の段階で見つかるわけです。
とはいえ、実際には、mm単位の間違いも
うやむやにすることはありません。
だからこそ、棟梁が建てた家は、何十年経っても
手入れさえしていれば、歪みや隙間が出てこないのです。

![]()
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
「建前」のときに
失敗が見つかることがあります。
それについて、僕らは
「間違いじゃないでね」と説明します。
というのも、
「完璧な家を建ててしまうと
その家主の家系は、それ以上繁盛しない」
と古くから言われているからなんですね。
間違いではなく、
施主さんを想ってのことだと説明するのです。
実際に、昔は、子どもや孫、ひ孫の代まで
ひとつの家に住んだので、
建物がその家系に大きく影響すると考えられていたのでしょう。
人から聞いた話なので、曖昧ですが
日光東照宮での話として聞いたものです。
この「1つだけ間違えると繁盛する」という
言い伝えから、棟梁は日光東照宮の繁盛
……つまり、徳川家の繁盛を願って
柱を一本だけ逆さまにして建てたそうです。
ただし、間違えていることがわかると大問題ですので
わからないように、その柱には彫刻を施したそうです。
ところがお披露目のときに、名も無いおばあさんに
「なんで、この柱だけ上下を間違えたまま建てたのか」
と指摘されてしまいました。
それを聞いた棟梁は責任を負って切腹した
という言い伝えがあります。
職人が素人に間違いを指摘されたわけですから
戦国時代なら、確かに切腹もあり得るかもしれません。
棟梁は、それぐらいに間違いにはシビアであり
将軍の「繁盛」は、今では想像できないぐらいの
とても重要なものだったのでしょうね。
僕の建てる家で見つかる間違いは、
もちろん小さなものです。
『つか』といって屋根の重さを分散して伝えるための
45cmぐらいの小さな柱があるのですが、
その長さを1cm5mm間違うなどの小さな失敗です。
僕らも、三度は確認するんですが
何千もの部材を使うわけですから
どうしても見落としが出てしまい、
それが建前の段階で見つかるわけです。
とはいえ、実際には、mm単位の間違いも
うやむやにすることはありません。
だからこそ、棟梁が建てた家は、何十年経っても
手入れさえしていれば、歪みや隙間が出てこないのです。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年03月17日
あなた自身が、参加する家造り!
【部屋のレイアウトは、あなたが考えてください】 ~設計に参加していただけます~
設計士や建築士でなければ、
「設計図が読めない」「図面が引けない」
と思っておられませんか?
長楽建築では、棟梁である僕自身が
CADを使って図面を引いています。
前回アップした、光と風が入るの設計図も、
もちろん僕が描いたものです。
それだけじゃなく、実は、
施主さんご自身が間取りの作成に参加できる
ということを、ご存じでしょうか。
最近は、無料で使える「間取り作成ソフト」が たくさんありますので、僕のオススメのソフトを ダウンロードしていただいています。
そして、まず、外枠だけ僕が描いて、
施主様に、どんどんレイアウトしていただいています。
これが、「すごく楽しい!」と評判です。
自分のアイデアが、どこまで活かされるのか ドキドキわくわくするそうですよ!
施主様がレイアウトしたものを、メールに添付して送っていただき、 僕が棟梁の目でチェックして、フィードバックします。
そうやってやり取りしながら、 最終的な設計図ができあがります。
実際のやり取りを、少しだけお見せします。
お客様からのFAXと、それに基づいて設計した
僕が描いた設計図です。
ね、やってみたくありませんか?


棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
設計士や建築士でなければ、
「設計図が読めない」「図面が引けない」
と思っておられませんか?
長楽建築では、棟梁である僕自身が
CADを使って図面を引いています。
前回アップした、光と風が入るの設計図も、
もちろん僕が描いたものです。
それだけじゃなく、実は、
施主さんご自身が間取りの作成に参加できる
ということを、ご存じでしょうか。
最近は、無料で使える「間取り作成ソフト」が たくさんありますので、僕のオススメのソフトを ダウンロードしていただいています。
そして、まず、外枠だけ僕が描いて、
施主様に、どんどんレイアウトしていただいています。
これが、「すごく楽しい!」と評判です。
自分のアイデアが、どこまで活かされるのか ドキドキわくわくするそうですよ!
施主様がレイアウトしたものを、メールに添付して送っていただき、 僕が棟梁の目でチェックして、フィードバックします。
そうやってやり取りしながら、 最終的な設計図ができあがります。
実際のやり取りを、少しだけお見せします。
お客様からのFAXと、それに基づいて設計した
僕が描いた設計図です。
ね、やってみたくありませんか?


棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
2013年02月20日
~光と風がめぐる「和風建築」~
【明るい家庭は、明るい『家』から】 ~光と風がめぐる「和風建築」~
明るい家庭は「明るい家」から。
僕は、そう思っています。
そこで、前回も少し書きましたが
「光」と「風」が入る家を設計しています。

例えば、暗くなりがちな階段。
階段に光が入るように、踊り場に窓をつけたり、
部屋の階段側の壁に窓をつけたりします。
また、階段の手すりそのものに光を通すべく
手すりを本棚にするというアイデアを取り入れたこともあります。

自然の木材を、自然のままに。
木には、あまり色をつけません。
とにかく見えるところに、たくさん木を使います。
もちろん、お客様の好みと相談はします。
リフォームの場合は、光を取り入れるのが難しい場合
白いクロスを貼って、光の反射を考慮することもあります。
また、窓は大きく取っています。
窓が自在に大きく取れるのも、和風注文建築の良さでしょうね。
幅3600cmほどの大きな窓があれば、部屋は本当に明るいです。
キッチンの収納も、腰から眼の高さあたりに窓を取りつつ
造り付けの棚を足元と、上部につけることもできます。
僕は、設計をするときに
「シンプルイズベスト」をモットーにしており
本当は、「田んぼの田の字」と言われるような
昔の農家が原点だと思っています。
田の字のように、和室がいくつもあり
普段は、ふすまでプライバシーが区切られている。
でも、冠婚葬祭のときなどは、ふすまを取り払うと
50~60人が入れる広間になる。
壁が少ないので、とっても明るく、風通しがいいんですねぇ!
それでいて、昔ながらの大工さんの経験に基づいて
とてもしっかり造られていたのです。
とてもよく考えられていると思いませんか?
そうやって、人がお互いの家に集まっていたんですよね。
最近は、プライバシーを確保するようになってきていて
どうしても、各部屋をバラバラに配置したりします。
そして、さらにプライバシー確保のために
部屋と部屋の間に、押し入れやクローゼットなどの
収納スペースを造る。
そうなると、風と光は通りにくくなってしまう。
もったいないですね。
デザイン性を重視して、小さい窓をいくつも入れるのが
好まれた時代もあります。これも風と光は通りにくい。
また、昔の農家は、水道がなかったので
台所は、土間になっていて、大きな瓶(かめ)があり
裏庭にある井戸に出入りできるようになっていました。
裏庭には、せっちん(トイレ)もあって
家人の排泄物は、田畑に使われ、
その農作物を食べて、暮らしていたわけです。
まさしく、「循環」ですね。
昔の家には、「循環」があったんですよね。
風と光、人間関係……
すべて風通しがよくて
すべてがめぐっていたんでしょうね。
少しずつ、そんな和風建築の良さが見直され
注文が増えつつあるのは、とてもうれしいことです。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら
http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください
明るい家庭は「明るい家」から。
僕は、そう思っています。
そこで、前回も少し書きましたが
「光」と「風」が入る家を設計しています。

例えば、暗くなりがちな階段。
階段に光が入るように、踊り場に窓をつけたり、
部屋の階段側の壁に窓をつけたりします。
また、階段の手すりそのものに光を通すべく
手すりを本棚にするというアイデアを取り入れたこともあります。
自然の木材を、自然のままに。
木には、あまり色をつけません。
とにかく見えるところに、たくさん木を使います。
もちろん、お客様の好みと相談はします。
リフォームの場合は、光を取り入れるのが難しい場合
白いクロスを貼って、光の反射を考慮することもあります。
また、窓は大きく取っています。
窓が自在に大きく取れるのも、和風注文建築の良さでしょうね。
幅3600cmほどの大きな窓があれば、部屋は本当に明るいです。
キッチンの収納も、腰から眼の高さあたりに窓を取りつつ
造り付けの棚を足元と、上部につけることもできます。
僕は、設計をするときに
「シンプルイズベスト」をモットーにしており
本当は、「田んぼの田の字」と言われるような
昔の農家が原点だと思っています。
田の字のように、和室がいくつもあり
普段は、ふすまでプライバシーが区切られている。
でも、冠婚葬祭のときなどは、ふすまを取り払うと
50~60人が入れる広間になる。
壁が少ないので、とっても明るく、風通しがいいんですねぇ!
それでいて、昔ながらの大工さんの経験に基づいて
とてもしっかり造られていたのです。
とてもよく考えられていると思いませんか?
そうやって、人がお互いの家に集まっていたんですよね。
最近は、プライバシーを確保するようになってきていて
どうしても、各部屋をバラバラに配置したりします。
そして、さらにプライバシー確保のために
部屋と部屋の間に、押し入れやクローゼットなどの
収納スペースを造る。
そうなると、風と光は通りにくくなってしまう。
もったいないですね。
デザイン性を重視して、小さい窓をいくつも入れるのが
好まれた時代もあります。これも風と光は通りにくい。
また、昔の農家は、水道がなかったので
台所は、土間になっていて、大きな瓶(かめ)があり
裏庭にある井戸に出入りできるようになっていました。
裏庭には、せっちん(トイレ)もあって
家人の排泄物は、田畑に使われ、
その農作物を食べて、暮らしていたわけです。
まさしく、「循環」ですね。
昔の家には、「循環」があったんですよね。
風と光、人間関係……
すべて風通しがよくて
すべてがめぐっていたんでしょうね。
少しずつ、そんな和風建築の良さが見直され
注文が増えつつあるのは、とてもうれしいことです。
棟梁
長楽 加藤建築 ホームページはこちら

http://www.nagara-katou.jp/
ながらの母ちゃんことかかのブログもご覧ください